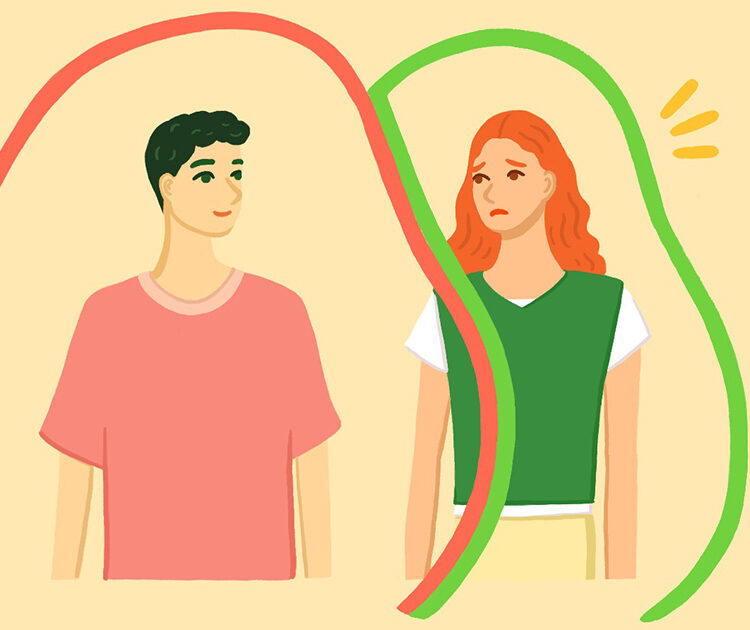生理について語りにくいのはなぜ? 社会の中でより快いものにしていくためには。田中ひかるさんインタビュー

初経から平均でおよそ38年間、毎月訪れ続ける生理。「フェムテック元年」とも呼ばれる2020年頃を境に、さまざまな生理用品も増え、かつてよりも生理について共有しやすい空気が生まれてきた一方で、まだまだ十分ではない側面も。生理と共に生きていく体を、この社会の中でより快いものにしていくためには、どのようなことが必要なのでしょうか。『生理用品の社会史』などの著書を持つ、歴史社会学者の田中ひかるさんにお話を伺いました。

たなか・ひかる。女性に関するテーマを中心に、執筆・講演活動を行う。『生理用品の社会史』(角川ソフィア文庫)、『月経と犯罪 〝生理〟はどう語られてきたか』(平凡社)、『明治のナイチンゲール 大関和物語』(中央公論新社)、『明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語』(中央公論新社)、『「毒婦」 和歌山カレー事件20年目の真実』(ビジネス社)などの著書がある。
──社会の中での生理の捉えられ方や語られ方の変遷について、歴史的な経緯も踏まえてお伺いしたいです。
田中:かつて生理は「ケガレ」と言われていましたし、「男の人に悟られてはいけない」「ナブキンを見られてはいけない」という時代が長く続きました。2020年が「フェムテック元年」と言われていて、そのあたりから、これまで話されてこなかったけれど、生理についてもっとオープンにしようという流れが起こったんです。生理については、オープンに語るべきか否か、どちらか一方の論調になりがちなのですが、2つの側面があると思います。
──どのような側面があるのでしょう?
田中:生理現象としての生理というのは、もちろん隠す必要がないことです。それを話してはいけない雰囲気があると、生理痛が辛いから生理休暇をほしいといった声をあげづらくなるので、必要に応じて口に出せることは、すごく大事です。一方で、プライベートな事柄であり、生理は「シモの話」という側面も否定できないので、話題として避けたり隠したりしたい人は一定数いると思うんです。生理自体に個人差があるように、羞恥心にも個人差があることは尊重しなければならないと感じます。
──生理について広く語られる機会が増えたのは、先ほどおっしゃられていたように、フェムテックのムーブメントの影響が大きいのでしょうか。
田中:ナプキンが普及したときもそうなのですが、やはりコマーシャリズムの力は大きいです。先んじて欧米で生理ブームがあったことや、国の後押しもあって、徐々にフェムテック製品がつくられるようになり、海外から吸水ショーツなど、日本にはなかったアイテムが入ってきて、国内の大手メーカーもつくり始めたことで一気に普及しました。製品をつくった企業が宣伝をしようとするなかで、生理について語られる機会は増えたと思います。
同時に、『生理ちゃん』や『パッドマン』のようなエンターテイメント作品の影響も感じます。また、SNSによって、生理用品や生理に関する自分の辛さについて、匿名で発信できるようになったことも大きかったのではないでしょうか。当事者自身が話題にしづらくて不便だと感じていたところに、そうした流れがあって、以前よりも生理について話しやすい空気が生まれてきたんだと思います。

──最近ではNHKの朝ドラ『虎に翼』でも、主人公の寅子は生理がとても重いという設定でしたね。
田中:これまでドラマなどで生理が描かれるとき、お腹を押さえてしゃがみこんだりするような、生理が重い人の描写が多い印象でしたが、『虎に翼』では、寅子は寝込むほど生理が重いけれど、同級生のよねさんはそうではないという設定だったので、症状に個人差があるということがきちんと描かれていると感じました。
──実際、生理のつらさは人によってかなり異なりますよね。
田中:生理は、人によって症状にも差があるけれど、そうした基本的な知識が伝わりきらないまま、「生理中はとにかく大変だからいたわろう」と一辺倒になってしまったり、「恥ずかしくもないし隠す必要もないんだから」と、場合によってちょっと露悪的に表現されることがあると感じます。
キラキラしていたり、ポジティブすぎる生理用品のCMも、快適さを表現するうえで広告として仕方ない側面はありますが、一面的な価値観を発信してしまうことには問題があると思います。いろいろな症状や感じ方の人がいることを踏まえて発信しないと、当事者にとって良い方向にはいかないと思うんです。人それぞれであることを否定しないことが大事だと思います。

──個人差があることを前提にしないことで、どのような問題が起こりうると思いますか?
田中:生理が重くて、生理のときに休みたい人はいますよね。生理に限らず体調不良のときに休む権利はあるし、休める社会でなければいけないと思うんです。だから生理休暇を取りやすくしたり、生理休暇という名前では休みを取りづらい人のために、企業によって違う名前にする動きが出てきたのは、いいことだと思います。
一方で、鎮痛薬や低用量ピル、ミレーナなど、医療的な選択肢で、生理の辛さを軽くして働いたり活動したいという考え方の人もいるわけです。どのような対処法を選択するかは人によりますが、色々な方法があることを知識としてもっと広める意味でも、「生理のときって大変なんです」というだけで終わってはいけないと思います。
──生理をめぐってはまだまだ情報の格差もありますね。
田中:たとえば中学生や高校生だと、受験や定期テストと重ならないように生理をコントロールしている生徒とそうでない生徒で、成績に差が出てしまうこともあります。生理の貧困の問題とも繋がるのですが、生理にともなう不調について、早めにケアしてくれる家庭もあれば、ナプキンさえ買ってくれない家庭もあります。そういう家庭では当然ながら、ピル代などの医療費も出してはくれないでしょう。つまり生理に対するケアの格差もとても大きいんです。生理用品や生理痛への対処法に選択肢があることを知らない人も少なくありません。当事者が自ら選択するために、情報が伝わっていくことが大事ですね。
──当事者以外が生理について知るための方法として、最近では疑似的に生理痛を体験するデバイスを使った企業向けの研修の様子などもニュースで見かけます。
田中:すべてのことがそうなのですが、誰かが背負っている辛さや苦しみについて、同じ体験をしないと、思いやりを持てないのかという意味では疑問を感じます。しかも生理の辛さというのは、生理痛だけではない複合的なものなので、同じ体験ともいえないんですよね。目の前にいる人が、「私は生理中にこういうことが大変だ」と言っていたら、それをそのまま受け止めることや、「じゃあこんなケアをしたらいいかな」と考えたりすることが大事だと感じます。

──社会の中で生理について適切な知識が広がっていくためにはどうしたらよいと思いますか?
田中:まず根本的には、初経教育が大切だと思います。生理への対処方法がたくさんある時代になったからこそ、生理用品や生理痛、月経前症候群の対処方法の選択肢、そもそも個人差があることを初経教育で知っておけたらいいですし、大人になってからも正しい情報を得られる機会があるといいですね。
それから、何か不調を感じたら、婦人科に行くことが大事ですね。婦人科の受診に抵抗を感じる方もいると思うのですが、歯科検診のような感覚で、婦人科に行けるといいですよね。生理の辛さを我慢する必要はないですし、「我慢しないで過ごす」というのが、その人自身にとってどういうことなのか、知ることができるといいですよね。当事者が自分たち自身のために、生理について語りやすい世の中であることが理想です。
text_Yuri Matsui photo_Mikako Kozai edit_Kei Kawaura