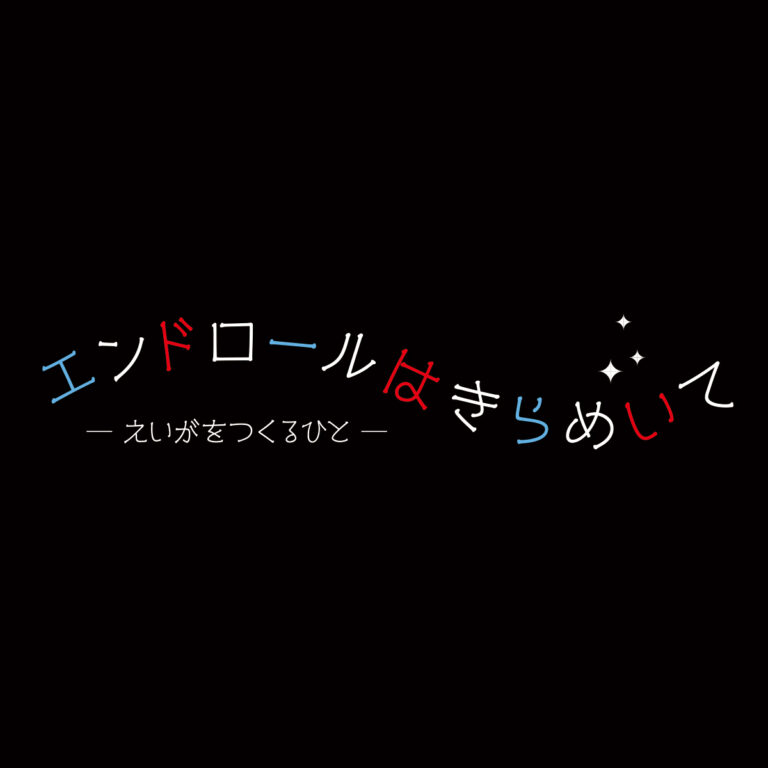16歳から、地道に泥臭く書き続けて。
映画文筆家・児玉美月|エンドロールはきらめいて
〜えいがをつくるひと〜 #13
毎月1人ずつ、映画と生きるプロフェッショナルにインタビューしていくこのコーナー。
第12回までは、映画の制作過程に携わる方々を紹介してきました。コーナー2年目を迎えた第13回目以降は「映画を広める人」に焦点を当ててお話を伺っていきます。
今回のゲストは映画文筆家の児玉美月さん。大学で映画を学んで以降、特にジェンダー・セクシュアリティの表象に関心を寄せながら言葉を紡がれてきた児玉さんは、どのようにして映画と出会い、どんなことを考えながら現在まで活動を続けられてきたのでしょう。
心の師は意外なあの人? 映画漬けの日々が始まったわけ
――児玉さんは今、パンフレットやコメントでお名前を見ないことがないくらい活躍されていますが、もともとはどのように映画に惹かれていったのでしょうか? 別媒体のインタビューで「明確に16歳から映画を観始めた」とおっしゃっていたのを目にしました。
16歳の時、とても辛いことがあって、引きこもりみたいな日々を過ごしていた時期があったんです。その時に偶然、妹がテニプリにハマっていたことがきっかけで、ミュージカル版に俳優として出演していた斎藤工さんのブログに辿りついて。内容がすごく個性的で面白く読んでいたら、その中で工さんが「映画の数だけ、人の人生がある」という言葉を残してらっしゃったんです。自分の人生を諦めかけていた当時の私には「映画を観たら、他の人の人生を生きられるかもしれない」と、その言葉が革命的に響きました。
そこから、家から歩いて3分の場所にあるTSUTAYAで片っ端から映画を観ていく生活を始めて。普通だったら名作と言われる作品や人気の作品から観始めるのだと思いますが、当時はまだインターネットの情報や映画の書籍にアクセスするリソースもないので、何もわからないままとにかく棚の端から全部観ていきましたね。引きこもりで一人だった長い時間、映画の中で他者の人生を生きることで、生き延びることができました。
ちなみに、雑誌の「好きな映画ベスト10」というような企画で工さんのラインナップを見かけると、私が観ていない作品をたくさん挙げいていらっしゃったりして。いまだに自分の映画の師匠という感じがします(笑)。
――TSUTAYA通いの後は、そのまま映画にのめり込まれて?
はい、その後すぐに「私は映画で生きていきたい」という思いが芽生えました。田舎から上京して大学では映画のゼミに入るんですが、そこで出会った先生が、結構強烈で。吉田羊さんのような雰囲気の方なんですが、授業で観せる映画がデヴィッド・リンチとかデヴィッド・クローネンバーグで、当時の自分からしたら、衝撃的な映画ばかりだったんです。今振り返ると発言の節々にフェミニズムを感じるような方でもあって。先生の授業を通して、新しく世界が開けた感覚がありました。
大学の4年間は誰に言われるでもなく、ひたすら映画館に通う生活を送って、とにかくいろんなジャンルの映画を観ていましたね。お金がなくて映画館に行けない日は、DVDが揃っている大学のAVライブラリーに一人で入り浸っていましたし。「絶対に年間500本見てやる」みたいな気合いがありました(笑)。
8月2日から4Kリマスターで公開されるデヴィッド・リンチ監督『デューン/砂の惑星』(1984年)予告編
「美しい」とは書かない。自らに課した批評のルール
――映画を観ることと文章を書くことは、児玉さんの中でどのように繋がっていったのでしょうか。
私はもともと記録オタクなところがあって、小さい頃から毎日日記を書いていたんです。学生時代も1本映画を観たら、必ず1ページを文字で埋めるようにしていました。ページが増やせるノートを使って、それが分厚くなっていくと嬉しい、みたいな。
こういうことを言うとマッチョだと言われてしまうかもしれないのですが、映画を観て文章を書くのは筋トレだと思っているんです。毎日のトレーニングをかかさず積んで、鍛錬してこそ書けると思っているので、目標値を設定して年間500本の映画を観たら、500本の文章を書く、というようなことを、16歳の時から続けてきました。それでもいざ真っ白の原稿を前にすると、いまだに「何を書いたらいいんだろう」とわからなくなることもあるんですが……。
――児玉さんレベルのトレーニングをこなしていても、書けない時があるんですか……!
全然あります! そういう時は、人の映画批評を読みまくるという別の筋トレをしてからまた考えます(笑)。とくに松浦寿輝さんや阿部嘉昭さんなど、詩人でもある方の書かれる映画の文章には何度も立ち返っています。傍から見たら、感性で書いてると思われている向きもあるような気がするのですが、実際に使っているのは筋肉なので、実は本当に泥臭いですね。
児玉さんが映画批評家として活動を始めた初期から参加している「Real Sound」の年間ベスト企画で2020年にベストとして選出した映画『燃ゆる女の肖像』(セリーヌ・シアマ監督、2019年)予告編。商業媒体に批評を書き始めたきっかけは、「誰も見ていない」と思っていたブログを編集者さんが見つけてくれたことだったのだとか
――児玉さんの文章は、映画史の中の位置付けなど客観的な視点をおさえながらも、感情に訴えてくる印象があります。多くのことを教えてくれるのに、説明的にならないというか、エンパワメントされるというか。
批評を書く時に「映画が主人公でなければいけない」「私が主人公になってはいけない」という禁欲的な部分はすごくありますし、自分は透明なまま後景化していい、ということは常に考えているのですが、とはいえ、漏れ出てくる感情があるならそれは捨てずに大切にしたい。意識的な客観性と無意識的な主観性がそこには共存しているのだと思います。
――過去に児玉さんが執筆された記事で「私」という言葉を使わない、と書かれていたのも印象的でした。他にもそうした決め事はありますか?
美しいとか、面白いとかつまらないとか、そういう感情に係る言葉は入れないようにしていますね。感情自体は観客であり読者であるその人だけのものなので、そこには立ち入らないように一線を引く感覚というか。もちろん「児玉さんが感じたことをエッセイ調で書いてください」というような依頼の場合は別ですが、通常の批評の場合は今言ったようなことを意識しています。
リスクを知りながらも、作品への批判をやめないわけ
それと、私は批評活動をするにあたって「批判」をすごく大切にしてきました。作品を批判することで自分の仕事を失う可能性だってもちろんありますが、おかしいと思ったことを言葉にしていかないと映画産業自体が廃れていってしまうだけです。なので書くべきことがあれば個人のSNSは当然として、パンフレットなど立場がオフィシャル側であっても、批判を書いてきました。もちろんそれは、批判が重要だと同じように共感してくださっている映画業界の方々がいてくださるおかげですが、そういう同志を少しずつ増やしていきたいです。
――作品を批判しようとしたら、画面に何が映っているのかを普段以上に注意深く見聞きして、慎重に言葉を使わなくてはいけない気がします。
批判は成功しないと意味がないんですよね。だからすごく難しいし、自分も身を削ってやっているようなところがあります。
それに魂を込めて批判をすると、新たな繋がりが生まれることもあるんです。最近もある監督から、私がSNS上で発信したとある作品に対する批判を見て「的を得ていると思ったから、自分の作品にも関わってほしい」と連絡をいただきました。今年トークイベントでご一緒した三島有紀子監督も、私が以前執筆した三島さんの映画に対する批判的な批評を読んだ上で「新作は絶対児玉さんにお願いしたかった」と言ってくださって。
批判に対して「作り手に対する攻撃」とか「悪口」と即物的な反応をされてしまうこともあるのですが、私は批判も映画批評の重要な営みの1つだと思っていますし、体裁を守るために、映画を褒めることしかしなくなったら、批評家としての自分にはもう価値がないと思います。
三島有紀子監督『一月の声に歓びを刻め』(2024年)予告編。児玉さんは公式のイントロダクションとストーリー文の執筆を担当し、コメントも寄せている
「書くことを恐れないでほしい」
――最後に、児玉さんが映画文筆家としての活動を続けられる中で感じる状況の変化があれば教えていただきたいです。映画をめぐる状況でも、文筆業をめぐる状況でも。
え〜、難しい! でも、私が映画を観始めた頃、きっと今から20年も経てばジェンダーやセクシュアリティの表象について書く映画批評家がたくさん出てくるだろうなと思っていたんです。ただ現状は、想像していたほどの状況にはなっていないかもしれない、という印象で……。
「SOGI(編註:性的指向と性自認を表す略称)」という言葉が生まれたように、ジェンダーやセクシュアリティに無関係に生きている人はいないので、本来はそれをテーマの一つに持つ映画であっても、書き手であれば誰もが書けるという状況が理想なはずです。
まず第一に当事者が語ることのできる土壌があること、その声をおざなりにしないという前提を共有できた上で、様々な立場の人が学びながら互いを尊重し合い、もっと高い水準で議論していけたらいいですよね。
――おっしゃる通りだと思います。時間を費やして言葉を紡ごうとするからこそ、新たな視点に気がつけることもあるのではないかと。
ジェンダーやセクシュアリティの分野は、とくに日頃から知識を更新していく必要性があると思います。私自身も自分の思考や言葉に問題がないか、新しい本や論文などに触れながら常に点検し続けていますし、不安と紙一重です。
去年、『彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家』(フィルムアート社)というフェミニズムの本を共著で発表したのですが、その本のコンセプトは一言で言うと「日本における女性の映画作家たちの批評言説を増やす」というものだったんです。でも「女性監督の本を作る」って、言ってしまえば誰でも思いつくシンプルな企画じゃないですか。その本が日本では2010年代以降なかなか本格的に出版されなかったという事実は、重く捉えるべきなんじゃないかと思いました。
書籍『彼女たちのまなざし』でも取り上げられた瀬田なつき監督による映画『違国日記』(2024年)予告編
なぜ欧米ほどこのテーマの書籍が数多く出版されていないのか、理由は複合的だと思いますが、わからなくはないんです。「女性映画作家」「女性監督」という言葉を取り扱うにあたっては、危うさも葛藤もあるだろうし、自分自身にとっても、それらは超えるのが難しいハードルでした。それでもこの本を書こうと思ったのは、まず何より「言葉にすることを恐れないでほしい」と伝えたかったからなんです。
文章を外に出すことは自分の恥部を晒すことと同じように恥ずかしいし、誰かを傷つけてしまうかもしれない暴力性が怖くて仕方ないことも日々あります。それでも恐れずに自分の考えたことや感じたこと、伝えたいことを言葉にすることで、きっと映画文化も、ひいては自分の人生も豊かになっていくはずです。その想いが、少しでも波及していけばいいなと思いました。「私も怖かったけど、書いたよ」と。これからもっともっと、映画についての対話が増えていけば嬉しいです。