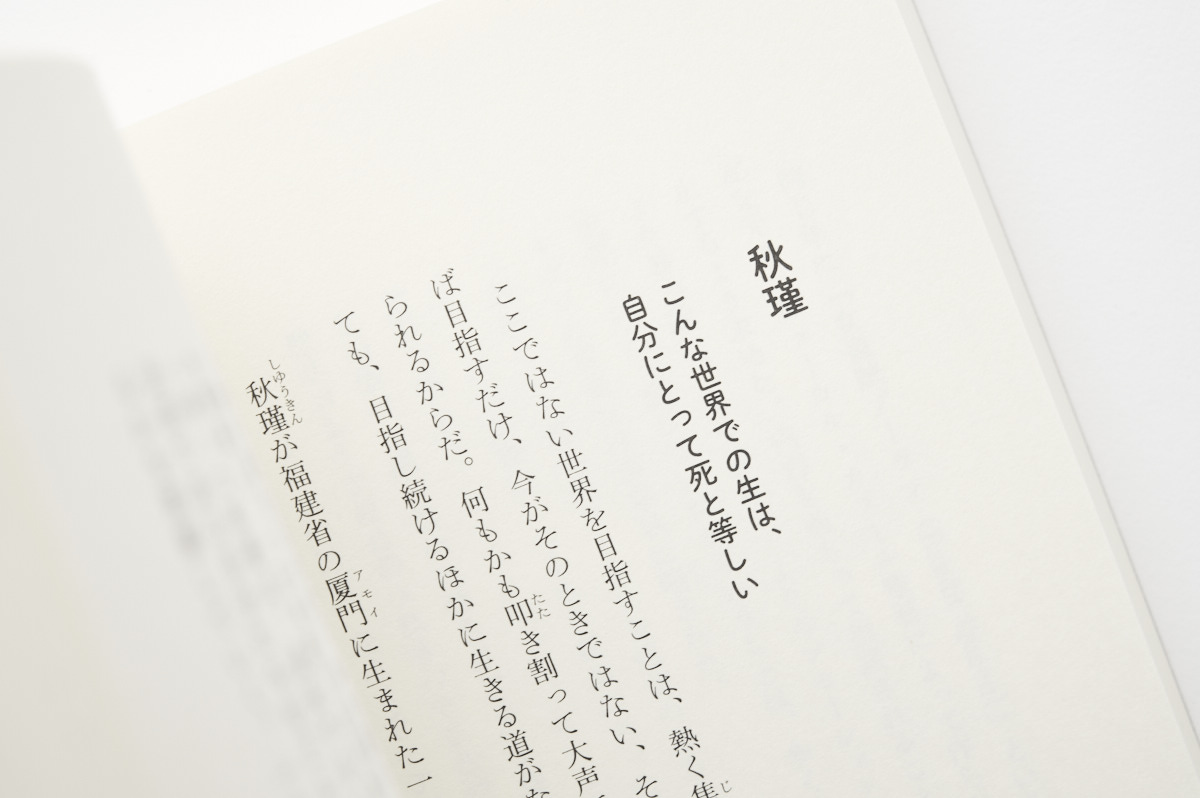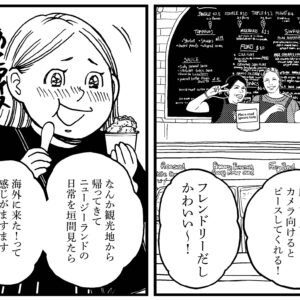男性社会に抗い 、功績を残したレジェンドの女性たち| はらだ有彩『「烈女」の一生』、小林エリカ『彼女たちの戦争』|きょうは、本を読みたいな #9
数時間、ときにもっと長い時間、一つのものに向き合い、その世界へと深く潜っていく。スマホで得られる情報もあるかもしれないけれど、本を長く、ゆっくり読んで考えないとたどりつけない視点や自分がある。たまにはスマホは隣の部屋にでも置いといて、静かにゆったり本を味わいましょう、本は心のデトックス。第9回目はライターの綿貫あかねさんが、はらだ有彩『「烈女」の一生』、小林エリカ『彼女たちの戦争』を紹介。
女性は何をするにも男性の許可が必要なのか?
「はて?」という主人公の猪爪寅子の口癖がじわじわくる今期のNHK連続テレビ小説『虎に翼』は、日本初の女性弁護士、三淵嘉子をモデルにしたドラマだ。寅子が女学生だった1930年頃は、結婚して夫を支え子育てし、良き家庭を作るのが女性の幸せとされていた。それは頭の回転が速く成績も申し分なかった寅子とて例外ではなかったが、見合いを強引に進める母に「自分の幸せが結婚とは思えない」と断って、大学の女子部に進学。男性しか認められていなかった法の世界へ飛び込んだものの、男社会でさまざまな差別や軋轢を体験していく。
当時の父権社会では少女の頃に飛び抜けた能力を発揮しても、寅子のように大学へ進学し、男性のテリトリーとされていた場所で活動できる人はほんの一握り。その多くは親や夫から家庭に押し込められ、才能や個性を抑圧されたり搾取されたりして、鋭利な輝きを摩耗させるしかなかった。それは『虎に翼』で描かれている時代よりはるか以前から一般化していて、「女性は男性の許可なく自由にふるまってはいけない」とされていたし、それを内面化させられていた女性がほとんどだった。
こういう物語に触れると頭に浮かんでくるのは、わたしが幼かった6、70年代に我が家で威張っていた父親や、傍で甲斐甲斐しく世話をしていた専業主婦の母親の姿と、そのときの決して明るくはなかった表情。なぜか習い事や部活の合宿参加には母ではなく父の許可が必要だったこと(父の機嫌を伺って切り出すよう母に促される)。子どもには「自分のことは自分でしなさい」と注意するのに、大人である父が自分の身の回りの世話を母にしてもらっているのは不平等ではないかという疑問。そう、不平等。学校でも家でも不平等を感じる場面で、少女のわたしは決まって不機嫌になっていた。
「そんな昔のことを言われても……」と困惑する人がいるかもしれないが、この社会通念は現代まで根強く継承されているのを日々感じる。男性が決めたことに女性を従わせるという男尊女卑的な思考は、妊娠中絶など性と生殖に関する問題や、一向に成立しない選択的夫婦別姓制度にも確実に影響を及ぼしていると思うのだ。
女性の人生は生まれたときから父や兄や夫という男性に決められ、やりたいことを自由に選べないという人権無視のあり方。それは今春ほぼ同時期に出版された、はらだ有彩著『「烈女」の一生』と小林エリカ著『彼女たちの戦争』からも十分に読み取れる。どちらも、その稀有な才能や血の滲む努力、輝かしい成果が不当に貶められ、歴史から消されてきた女性たちが主役のエッセイ集だ。
したいことをしようとした女性の生き方を知る『「烈女」の一生』。
『「烈女」の一生』は、カレーで有名な新宿中村屋を創業した相馬黒光や、メキシコの画家フリーダ・カーロ、ユダヤ系の哲学者ハンナ・アーレントなど、主に20世紀前半に自己の信念に導かれ奮闘した国内外の女性20人のパイオニア的な生き方に焦点を当てている。
多くの少女小説を執筆した作家の吉屋信子の場合、雑誌の懸賞小説に入選するほどの文才を、親から嫁入りにはむしろ邪魔だと否定され、女学校卒業後に東京で勉強したいと望むも却下された、という話が紹介されている。ようやく上京が叶ったのは、唯一理解を示した兄の助力があったから(結局ここでも男の発言がものをいうのだ)。しかし信子が小説で女性同士の愛を描き続けたのは、女性は男性より劣った存在であり、男性に隷属して生きるものという通念を自ら内面化している多くの女性たちに、愛をもって支え合う女性同士の関係の安らかさを伝えたかったのではないだろうか、と想像させる。
絵画と文章で優れた才能を発揮した羅蕙錫(ナ・ヘソク)は、「そうしたい」と自由に思うことで何事も可能だと信じてきた女性だ。日本占領時代の朝鮮で、芸術活動を行いながら独立運動のサポートをしていた彼女は、出産でキャリアを中断する困難とも戦い、一家の稼ぎ頭でもあった。しかしかつての恋人に援助を求めた一通の手紙により、夫から離婚され子どもも取り上げられる。大金を払って建てた家も追い出された上、朝鮮の人々からも見放されてしまった。夫や元恋人はその後何事もなかったように暮らしているのに、女性だというだけでなぜ何もかも失い、社会から抹殺されなければならなかったのか。彼女の功績が再評価されるまで没後約40年かかったという事実を重く受け止めてしまう。
男性研究者に搾取された理系の女性に注目したい『彼女たちの戦争』。
女性は理系に向かないという固定観念は、近年ようやく見直す傾向になってきたが、『彼女たちの戦争』を読むとそれは本当に許し難い偏見であり、悔しさでいっぱいになる。この本には、アナキストの伊藤野枝や彫刻家のカミーユ・クローデルなどが取り上げられているが、特に大声で聞こえてくるのは、男たちが始めた戦争と呪縛のような差別のせいで、自分の望む道をたどれなかった理系の女性たちの魂の叫びだ。
たとえば、DNA二重らせん構造のX線写真撮影に成功したロザリンド・フランクリンの話。同僚だった男が、その写真を勝手に別の大学の研究者たちに見せたことで、その研究成果が横取りされてしまう。彼女はそれを知らないまま癌で亡くなったあと、その男たちがノーベル生理学・医学賞を受賞した。ひどい。
また、ベルリンで化学者の男と放射能の共同研究を始めたユダヤ系のリーゼ・マイトナーは、ナチスの台頭により亡命したスウェーデンから、手紙のやり取りを重ねて研究を続けていた。あるとき男から実験に関する手紙が届き、彼の甥と検証を重ねた結果、核が分裂していることを発見し、すぐに男に知らせた。しかし彼がその発見を論文にまとめ発表した際、そこに彼女の名前は一切なく、男たちだけがノーベル化学賞を受賞した。これもひどい。
研究者として互いに協力し合ってきたつもりだったのに、裏切られた無念さは計り知れない。女性がまるで男性のサポート役かのように搾取され、成果は男性だけが独占するのは不平等そのものだ。歴史に名が刻まれ功績を讃えられるのは男性だけで、女性は名前すら残らないなんて。
不平等に悔し涙を流し、努力して結果を残してきた偉大な女性のことを忘れてはならない。有名無名問わず、彼女たちが道を切り拓いてくれたから、今の私たちが前へ進めるのだ。抑圧を跳ね除け、ジェンダーギャップを改善する、その歩みを止めないようにしたい。この二冊の本は、私たちの背中を押し続けてくれるはずだから。
しかし、さらにこうも思う。彼女たちの功績や無念が十分に知れわたり、当たり前になったその空気のなかを、その次の世代の女性たちが軽やかに生きていく、そういう社会が理想なのだと。
『彼女たちの戦争』、『「烈女」の一生』
左・小林エリカ著。伊藤野枝、マルゴー・フランクとアンネ・フランク姉妹、ヴァージニア・ウルフ、湯浅年子…この女を見よ!活動家、科学者、詩人、作家…。「歴史」の中で不当に扱われ、不遇であった彼女たちのの横顔を拾い上げ、現在、未来へとつないでいく、やさしくたけだけしい闘いの記録。1,870円(筑摩書房)
右・はらだ有彩著。トーベ・ヤンソン、フローレンス・ナイチンゲール、マリー・キュリー、ハンナ・アーレント、吉屋信子…歴史に名を刻んだ女性たちは、その生の中で何を思い、行動したのか。20人の人生を、『日本のヤバい女の子』シリーズ等で注目を集める気鋭の著者が独自の視点で紐解く。1,870円(小学館)