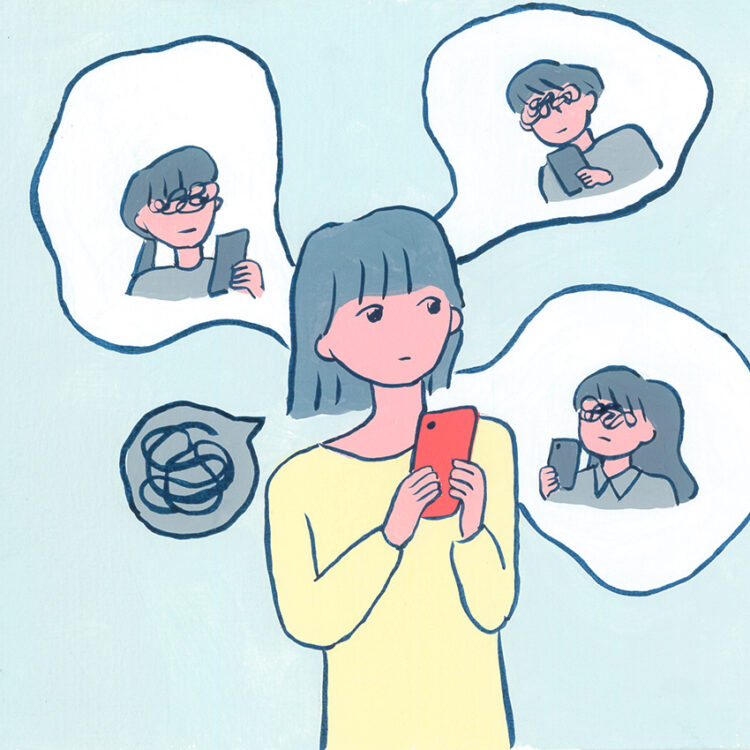“ちやほや”って本当に特権なのか。選択的夫婦別姓もクウォーター制も実現しない社会のなかで思うこと|松田青子エッセイ

※記事のスクショをSNSやWebページ上に掲載する行為は、著作権法違反、肖像権侵害、名誉毀損罪・侮辱罪に該当し、場合によっては法的責任を問われる可能性があります。

まつだ・あおこ/『おばちゃんたちのいるところ』がTIME誌の2020年の小説ベスト10に選出され、世界幻想文学大賞や日伊ことばの架け橋賞などを受賞。その他の著書に、小説『持続可能な魂の利用』『女が死ぬ』『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』(いずれも中央公論新社)、エッセイ『お砂糖ひとさじで』(PHP研究所)『自分で名付ける』(集英社文庫)など。
日本社会に蔓延する“ちやほや”の正体は?
女性は“ちやほやされてずるい”的な言説を見聞きすると、いちいちゾッとしてしまう。ぎゃー、出たーーー!!!と叫んで全力で逃げたくなる。
世の中の「ちやほや」の使われぶりにどうしても慣れないし、納得がいかない。
まず、女性は本当に「ちやほや」されているのだろうか。
「ちやほや」という言葉は、たいていの場合、若い女性に対して使われる。この社会的な文脈においては、歳を重ねると「ちやほや」されなくなる。
たとえば、最近、漫画『娘がパパ活をしていました』(グラハム子著/オーバーラップ)を読んだのだけど、その中で、主人公の高校生、千紘にパパ活をすすめる、すでにパパ活をしている友人はこう言う。
「年とったらできなくなるし 若いうちの特権だよ」
この「特権」は、「ちやほや」と太い一直線でつながっている。「ちやほや」されるから、若い女性たちには「特権」があるのだと、彼女たち自身が内面化しないと生きていけないほど、日本社会には「ちやほや」が蔓延している。
では、「ちやほや」とは、どういうことを言うのだろう。
若いことを褒められる。容姿を褒められる。しぐさや言動が「女の子らしい」「女性らしい」と褒められる。男性たちにとって都合のいい存在であると褒められる。
そして、そのことによって、男性に優しくされたり、何かを奢ってもらえたり、プレゼントされたりと、多少の”恩恵”があったりする。

でもそれじゃ「ちやほや」のレベルが低くないか。
「ちやほや」してくれる側が、性別や家庭環境など、あらゆる属性によって不均等な社会を変えてくれたり、男女の賃金格差を解消してくれたり、選択制夫婦別姓やクォータ制を導入してくれたり、それらの実現のために何か動いてくれたりしただろうか。「ちやほや」するっていうなら、それぐらいしてほしい。
そうしてくれたら、ちやほやしてもらった!!!と、高らかに認めたいけれど、実際のところは、何もしてくれていないし、むしろ、これまでのように女性を「ちやほや」するためには、多少の”恩恵”を本当に必要とする状況にある人たちを搾取するためには、それらが実現しないほうが好都合だろう。
(クォータ制というのは、政治における格差を是正するために、性別や人種などを基準にして比率を一定にするための制度なのだけど、数年前、イギリスのオックスフォード大学で学長をしている女性と話した際に、クォータ制が導入されて社会が本当に変わった、と彼女が淡々と、実感を込めて語るのを聞いて、日本でもその変化を経験してみたいとずっと思っている。
あと、こういう話題の時に、性別などで優遇されるのではなく、能力がある人が務めるべきだ勢が必ず湧いてくるけれど(他の分野においても全般的に言えることだけど)、これまで、そして今、重要とされる役職に就いている男性たちの能力が本当に高く、仕事ができるのならば、もっとずっといい社会で私たちは暮らしているはずだ。そこをもうちょっと考えてほしくなる)
ナメられたり、都合よく扱われたりしない社会のほうがずっといい
現状の「ちやほや」は、モラハラやマウンティング、そして『娘がパパ活をしていました』にも描かれているけれど、セクハラや性的暴行などの性犯罪が延長線上にある。
そんな「ちやほや」は「ちやほや」じゃないし、こんな状況下で、若い女性は「ちやほや」されていると、勝手に誰かに思われているのも心外だし、気持ちが悪い。
若い頃に自分は「ちやほや」されたと思っている女性も少なくないけれど、本当の意味で「ちやほや」されていたのだろうか。
私は若い頃に、自分は「ちやほや」されていると思ったことが一度もない。むしろ、ずっと馬鹿にされている、ナメられていると感じていた。
たとえば、これはもう30代も後半のことだったけれど、私がエッセイなどをいろいろ書いていることに対して、「小説に集中したほうがいい」と、ある年上の男性作家に“アドバイス”されたことがある。
「エッセイとかを書いてお金を稼がなくても、松田さんだったら編集者たちがごはんをおごってくれるから大丈夫だよ」
というようなことをその人は続けたのだけど、これもナメがたいがいの案件で、なぜごはんをおごってもらったら、それだけで生きていけると思っているのだろうと呆れた。
念のために書くと、打ち合わせの延長で一緒に食事をすることはあるけれど、編集者さんたちは毎日ごはんをおごってくれるために存在する人たちではもちろんないし、毎日ごはんをおごってもらいたくもない。
あと、その人は、私が2013年に最初の小説が刊行されて以来、書くことと翻訳することだけで生活できていると言うと、「え!」と驚いた。まさか私ごときにそんなことが可能だと思ってもみなかったらしい。
この例は少しずれているけれど、自分も家に住んで、家賃や光熱費や税金を払って生きているのに、自分よりも若い女性の生活や仕事への想像力が乏しすぎる一例にはなるし、こういう脳内の人が多いから、「ちやほや」幻想が廃れないんだろうなと考えてしまう。
食事をおごってもらったり、プレゼントされたりすることよりも、自分で生きていける経済力を持つことのできる社会のほうがいい。容姿や言動を他人にどうこう言われない社会がいい。都合よく扱われない社会がいい。年齢や性別、その他の要因でナメられない社会がいい。それだけだ。
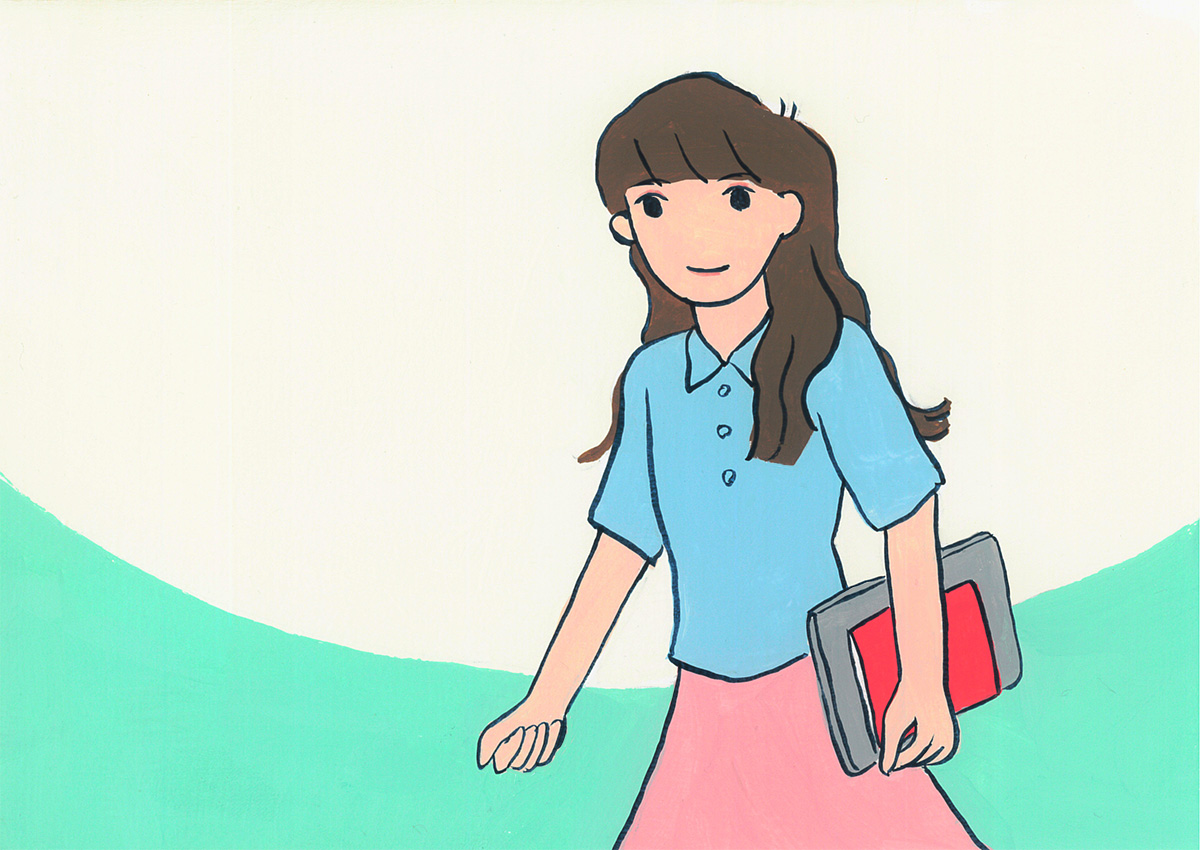
text_Aoko Matsuda illustration_Hashimotochan Edit_Hinako Hase