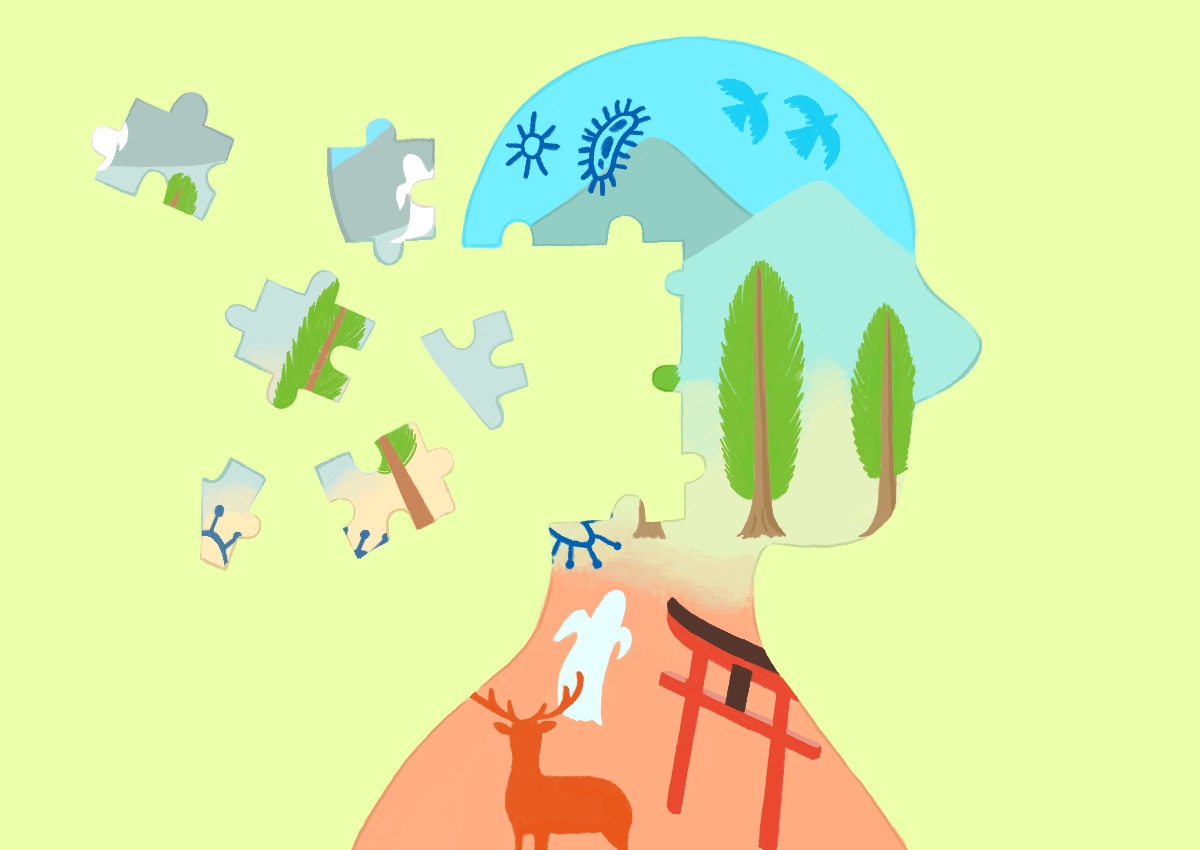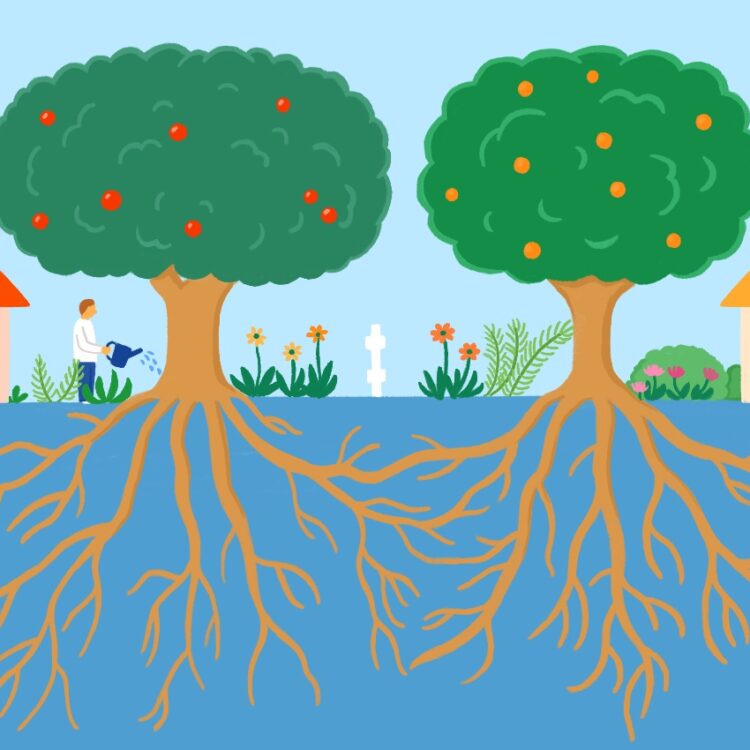「利他」は「支配」と紙一重? 互いに“与えあう関係”をつくるために必要なこと

※記事のスクショをSNSやWebページ上に掲載する行為は、著作権法違反、肖像権侵害、名誉毀損罪・侮辱罪に該当し、場合によっては法的責任を問われる可能性があります。

東京科学大学(旧・東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。京都大学大学院博士課程修了。専門は南アジア地域研究、日本思想史。著書に、『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』(朝日文庫)、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『思いがけず利他』(ミシマ社)など。

東北芸術工科大学非常勤講師。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。著書に『大杉栄伝 永遠のアナキズム』(角川ソフィア文庫)、『死してなお踊れ 一遍上人伝』(河出文庫)、『超人ナイチンゲール』(医学書院)、『幸徳秋水伝 無政府主義者宣言』(夜光社)など。
我知らずで動いたとき、人は想像を超えた力を発揮する
中島岳志さん(以下、中島):第一回では、メディア研究が専門の伊藤昌亮さんと「ひろゆき&石丸現象」を題材に、今の日本に蔓延る“セコイ自己責任”とその背景について分析し、続く、第二回では、英文学者の小川公代さんと、近代社会でよしとされてきた“自己の在り方”を見直し、自己責任社会を乗り越えるための「ケア」や「利他」の視点を深堀りしました。
そして最後に栗原さんとお話したいテーマが「自己責任社会を乗り越えるためには、私達はどんな人間観を育てていかなくてはいけないのか」ということです。
栗原さんは「アナキズム(※1)」、私は「保守」というまったく異なる視点から、利他やケアといった言葉で表現される人間の在り方について考えていて、そこに、今の日本に蔓延る「自己責任社会」を突破する、人間の根源的な可能性があると考えています。
栗原康さん(以下、栗原):そうですね。実は私も真逆の立場から同じことを言っている方がいるなと思っていました(笑)。
私がこれまで評伝を執筆したナイチンゲールはケアや神秘主義(※2)、アナキストの幸徳秋水(※3)は東洋思想の自然(じねん)(※4)といった思想を持っていて、これは中島さんの著書「思いがけず利他」(ミシマ社)の“思いがけず”の部分と重なるんです。
彼らの共通点は、個人主義、合理主義が前提にある、“近代的な自己”を想定していなくて、「私が〜」という主格的な視点、つまり「自分にとって損か得かで行動する」という原理では動いていない。
近代の人為的に作られた社会では、損か得か、善か悪か、優か劣かといった二項対立でものごとを捉えがちですが、それを飛び越え無為に生きている。
自由意志すら振り切って、目的にとらわれることなく、自ずから呼びかけられて動いてしまうような感じですね。これは別に一部の特別の人が持っている感覚ではなく、人間という生物の根源にあるものじゃないかと思っています。
孟子の『仁は人の心なり(思いやりは本来、人が持っている心である)』という言葉はまさしくそれを表しています。
例えば、幼い子どもが井戸に落ちそうになっていたら、損得顧みず助けてしまうものであり、子どもの服がきらびやかだからお金がもらえるとか、そんなことを考えて助ける人はいないですよね、と。
人は主格を飛び越えて、我知らずで動いてしまうときがある。利益を意識するのではなく、利他の利すら消えたときに、人はものすごいパワーを発揮します。これは、人と人はもちろん、人と動物や植物などあらゆる関係性の中でベースにある非常に重要な考えだと思います。
中島:「ケア」や「利他」を考えるうえで、「思いがけず」言い換えれば「〜しちゃう」っていう部分が私もすごく重要だと思っていて、“どうしようもなさ”みたいなものが溢れている姿ってなぜか人の心を打つんですよね。「本当に好きなんだ」「本当に謝っているんだ」と真心を感じさせる力があり、みんな無意識に発揮していますよね。
「〜しちゃう」の本質を鋭く表現しているのが志賀直哉の『小僧の神様』という小説だと思います。舞台は大正時代の神田。エリートである貴族院議員のAが街を歩いていたら、小僧が寿司を食べたくて屋台の前でモジモジしている小僧を見かけます。
小僧は、思い切って屋台の中に入ったもののお金が足りなくて出ていく。それを見ていたAは、「かわいそうなやつだな。今度彼にあったらたらふく奢ってやろう」と思います。1ヶ月後、Aは偶然小僧と再会し、寿司をご馳走します。
しかし、面白いことにAは嫌な気分になってしまうんですね。自分がやろうと思ってやったいいことのはずなのにどうしてだろうと。それを妻に言ったら「わかる気がする」と言われます。
利他的な行動をしているはずなのにモヤモヤするのはどうしてか。
Aは初めて小僧を見かけたときにとっさに体が動いていないんですよ。もし、最初に出会ったときに「食べなよ」ってご馳走していたら、そういったわだかまりはなかったと思います。
でも再会したときにご馳走したのは、憐れみの感情に基づいた“意思的な行動”になってしまっていて、これがモヤモヤした感情を生んでいるのはないでしょうか。
何かを与えることは、支配関係というリスクがつきまとう
栗原:“意識”が入ったとたんに、与える側、与えられる側という関係性が固定されてしまいますよね。
私の友人である北川眞也さんはイタリアの移民問題などを研究していて、著書『アンチ・ジオポリティクス 資本と国家に抗う移動の地理学』(青土社)の中に移民を救おうと活動している神父さんが登場します。
もちろん、神父さんはキリスト教に基づいた純粋な良心で移民の人々に寝床や食事を提供しているのですが、それが続くうちに、移民と神父の間に主従関係が生まれてしまう。
神父さん自身は、支配しているなんて思っていないけれど、もてなされた側は感謝の気持ちから、神父には何でも従うようになってしまうわけです。
一対一の関係の中で、「与える」や「助ける」といった意識が介入すると、どうしても与える側が偉くて、もらう側は恩返しのためにその人に従わないとと感じてしまうし、逆にもらうのが当たり前となってしまうと、与える側は無償で奉仕し続ける奴隷のような状態になり、どっちにしろ支配関係が生まれてしまいます。
その視点が抜け落ちると「利他」や「ケア」は人格的支配関係にもつながる紙一重で危うい部分があるなと思います。
中島:今、栗原さんが指摘された部分が「贈与」という問題を考えるうえで最もポイントになると感じています。
『贈与論』の著者であるフランスの文化人類学者のマルセル・モースは、「ギフト」という概念について、「誰かにものをあげる」に加え、「ポイズン(毒)」の意味があると論文の中で書いています。
つまり、ギフトで与えているのは単に物だけではなく、負債感も与えていて、与えることは支配にもつながると指摘しているんですね。
実際、私達は何か贈り物をもらうと、そのときは嬉しいんだけれど、しばらく時間が経つとどうお返ししようか悩んだり、返せていない状況でさらに贈り物をもらうと精神的な負担を感じると思います。
人類学では、ネイティブアメリカンの儀礼「ポトラッチ」を例に贈与のポイズン的な側面を説明しています。これは、ある部族が別の部族を豪華な宴に招き、財産や贈り物を配って破格のもてなしをすることで、「これを返すことができるか」とマウントを取る競争的な贈与儀式で、お返しができなかった場合、二つの部族には上下関係ができます。
栗原さんがおっしゃったように、贈与は支配という問題が常に絡んでくる。では、贈与につきまとう支配関係を超えて、「ケア」や「利他」を開いていくにはどうしたらいいのか。
私はそれを考えるヒントとして「フランシスコの平和の祈り(※6)」の中にある「与えることは受け取ることである」という考え方がとても重要だと感じています。
例えば、子育ても一方的に与えているようにみえて、子どもから与えられていることのほうが圧倒的に多い。また、大学で学生を指導しているときは、学生たちに感化されて自分が動かされてしまったり。
自他の境界が消えたとき、ケアや利他は本物になる
栗原:私は受け取るのが好きな人なんですね。例えば、面白いと思うことがあれば深夜であろうと友達に電話をかけて、話を聞いてもらったりしています(笑)。
ただ、最初は自分の話を聞いてもらっているんですが、相手ものってきて、最近あった面白い本の話とかをしてくれて、互いにワーっと話が止まらなくなる。
すると、次第にどっちが話しているのかわからなくなって、与える側、与えられる側とか自他の境界線が消えていくんです。自分の中に相手が紛れ込んできて、無意識のうちに相手からいろいろなものをもらっているんですよね。

他者との関わり合いって、ギブ・アンド・テイクではなく、ギブ・ギブ・ギブ…あるいはテイク・テイク・テイクの連続による支え合いだと思います。
中島:私もまったく同じような経験をしたことがあります(笑)。批評家の若松英輔さんとの対談をまとめた書籍『現代の超克』(ミシマ社)は、対談の過程でどっちが言ったのかわからなくなり、「どっちが言ってもいいよね」なんて言ってできた一冊です。
でも、人間ってそもそもオリジナリティってほとんどないと思うんですよ。先人たちの言葉に背中を押されて私達は何かを言っているだけ。私が親鸞を好きなのは自力、つまり自己のオリジナリティを徹底的に疑っているからなんです。
人間は器であり、死者や自然といった他者からやってきたものを受け取って存在していて、そこにはもはや自他の境界なんてありません。
栗原さんが評伝を書いているナイチンゲールもそうですが、他者の感情の中に自分を投じることで、自由意志とか目的というものから完全に自由になる。そうして初めてなされるが本当の意味での「ケア」や「利他」だと思います。
近代的な自己の在り方とは対局にある、自他の境界を飛び越えてしまうような在り方の先に自己責任社会を乗り越えるを可能性を見いだせるのではないでしょうか。
※1:アナキズム|古代ギリシア語の「arkhē(アルケー、統治・支配・原理・根拠)」という言葉に否定の接頭辞「an(アン)」が付いた「anarchy(アナーキー)」と「ism(イズム、主義)」から構成された言葉。「無政府主義」や「無支配主義」と訳される。暴力のみならず、経済的、社会的なあらゆる手段において人間を支配することを認めないという発想。
※2:神秘主義|神やその摂理、宇宙の理を絶対視するのではなく、直接体験しようとする考え方。
※3:幸徳秋水|明治時代のジャーナリスト、思想家、共産主義者、社会主義者、アナキスト。
※4:自然(じねん)|「自ずからそうあること。本来そうであること。ひとりでに」を意味する東洋的思想。
※5:フランシスコの平和の祈り|13世紀にイタリア半島で活動したフランシスコ会の創設者、アッシジのフランチェスコ(聖フランシスコ)に由来するとされた祈祷文。フランチェスコ自身の作ではないが、フランチェスコの精神を十分に表しているとされている。
illustration_Natsuki Kurachi text&Edit_Hinako Hase
▼他連載記事はこちら
「自己責任社会を乗り越えるために必要な人間観」の後編を配信します。そちらもぜひ、ご覧ください。