人間は間違えやすい。“自立した個”が重視される世界で、私たちが見落としがちなもの

※記事のスクショをSNSやWebページ上に掲載する行為は、著作権法違反、肖像権侵害、名誉毀損罪・侮辱罪に該当し、場合によっては法的責任を問われる可能性があります。

東京科学大学(旧・東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。京都大学大学院博士課程修了。専門は南アジア地域研究、日本思想史。著書に、『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』(朝日文庫)、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『思いがけず利他』(ミシマ社)など。
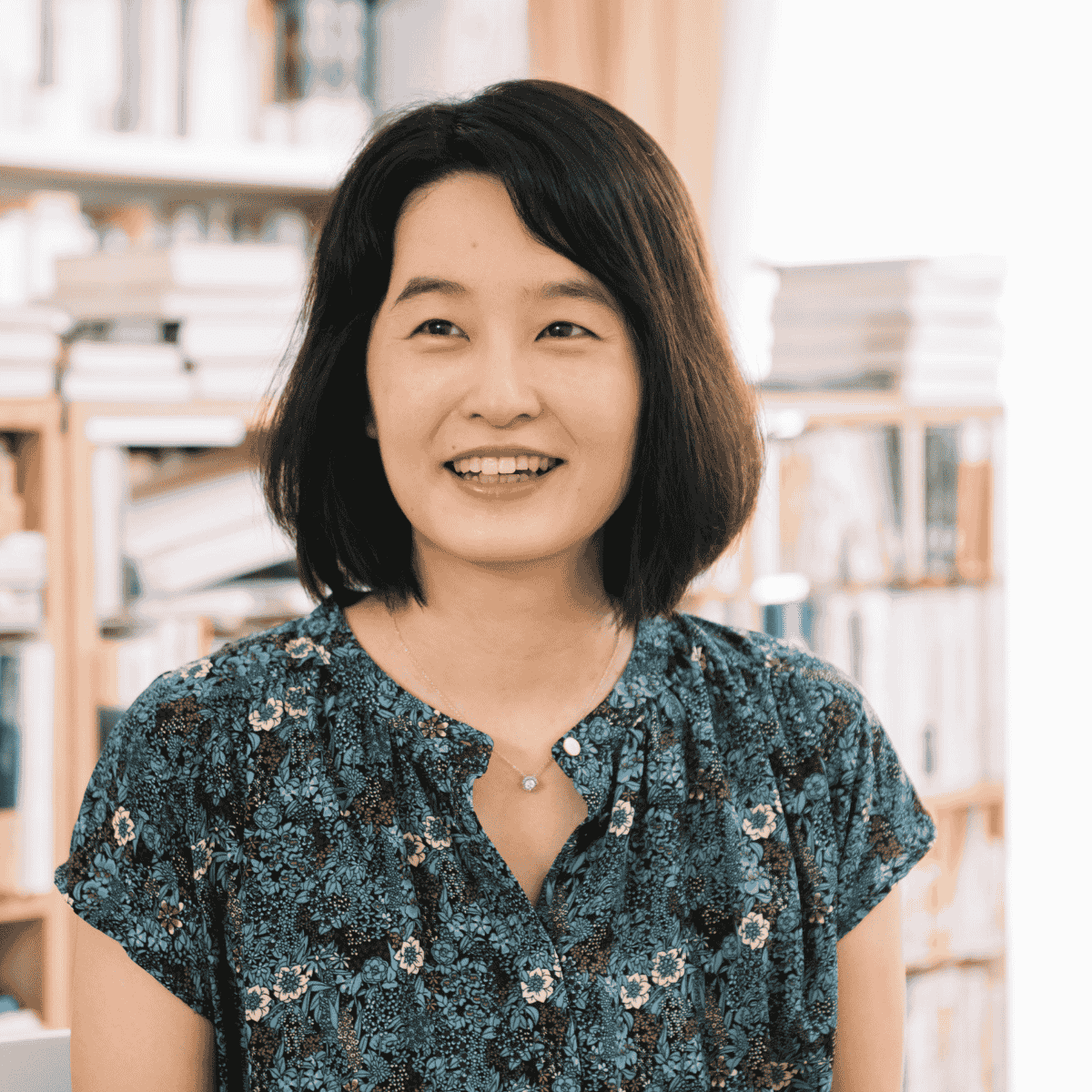
上智大学外国語学部英語学科教授。英国グラスゴー大学・文学部(英文学)博士課程修了。医学史、精神医学史、ジェンダー、ポスト・コロニアリズムといった観点から文学作品を分析。著書に、『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)、『世界文学をケアで読み解く』(朝日新聞出版)など。
撮影 : 嶋田礼奈
言葉では捉えきれない“間”にある「ケア」と「利他」の本質
中島岳志さん(以下、中島):「自己責任」をテーマとした対談Vol.1では、伊藤昌亮さんと「ひろゆき&石丸現象」を題材に、今の日本に蔓延る“セコイ自己責任”とその背景について分析をしました。
その中で、“責任”は英語で“responsibility”、つまりレスポンス=応答することまでを意味する。「自分さえよければ」ではなく、社会や他者に応答をすることまでが本来の責任の在り方なんだということをお話したんですね。
私自身、ここ数年“利他”ということについて考えていて、その本質は「〜してあげたい」とか、「自分にとって得になるから」ではなく、「つい〜しちゃう」というAutomatic(自動的)なものだと感じています。
実はこの感覚、私が大学のころから学んできたヒンディー語の「与格」という言語構造に通ずるんです。
「私は〜」という主格に対して、与格では「私に〜」で文章が始まり、文法書には「私の行為や状態を私の意思に還元できない時に与格を使う」と書かれている。
例えば、風邪を引いた時には「私に風邪が留まっている」、嬉しい時には「私に嬉しさが留まっている」、さらに「私はあなたを愛している」なら「私にあなたへの愛がやってきて留まっている」となかなかロマンチックな言い方ですよね(笑)。
与格は、「自分の意思によって、自分をコントロールしている」のではなく、「私にやってくる何かの力がある」、あるいは「そういう力が内在している」そんな世界観なんです。
これって、誰かを“つい”気にかけて、“つい”関わってしまう「ケア」の在り方と結びつき、ここにこそ人間の大きな可能性があると私は感じています。
近年は、与格が主格に乗っ取られてきていて、これは言語における話に留まらず、自立した自己をよしとする近代において「ケア」というものがネガティブな文脈に置かれ、周縁化されてきた問題にも重なります。
小川公代さん(以下、小川):私もそう思いますね。
米国の心理学者、キャロル・ギリガンは著書『もうひとつの声で』の中で、「人の話を聞いてしまう」「他者の意見に追随してしまう」といった近代の個の観点からはネガティブな文脈に置かれがちな“揺らぎ”や“優柔不断さ”を、倫理的な“強み”として捉え直す「ケアの倫理」を提唱しました。
誰かを気にかけて動くケア的な在り方。そこには、否定も肯定もなく非常に与格的である。そう強く実感したのが、女性ホームレスの研究をしている丸山里美さんの著書『女性ホームレスとして生きる―貧困と排除の社会学』(世界思想社)を読んだ時でした。
丸山さんは、どんな女性がホームレスになるのか密着して研究をしていて、印象的だったのが、ホームレスの女性が援助を受けて、路上を抜け出したにもかかわらずまた戻ってしまうという場面。
たとえ自分には利益がなかったとしても、「あの人ちゃんと食べているかな」と一緒に路上生活をしていた人が心配になり、結局、引き寄せられるように路上に戻っていく。
それを読んだ時に「ケアってこれなんじゃないか」って思ったんです。自分の意思で動いているのでもなく、はたまた完全に誰かにやらされるのでもなく、その間にある言葉にできないもの。ケアの本質は与格としか表現しようがないと感じています。
近代的な思想では、自立を善としていますが、「能動的な活動ができる自立した自己」というのは、子育てや介護といったケアをしている人がいてはじめて実現可能になる。
たとえば、稼いで自立していたけれど、家族のケアが必要になり、どちらかを選ばなくてはいけない状況で、ケアを選んだとする。それって、能動的でも受動的でもなく、今の「リベラルか保守か」という二元論では捉えきれないものがあると思います。
理性を万能視しない。リベラルと保守が大事にする寛容という原点
小川:中島さんは著書『保守と立憲』(スタンド・ブックス)で、リベラルの起源は“寛容”であり、保守の考え方と対立するものではなく、実は親和性が高いんだということを書いていらっしゃいましたよね。
中島:はい。ヨーロッパで17世紀前半に起きた宗教戦争が終結した際、これ以上、価値観の問題で争うことを避けるため、自分とは相容れない価値観であっても、まずは相手の立場を認める「寛容」の精神が重要だという議論が生まれ、これが「リベラル」の起源です。
一方、保守の発端に位置付けられているのは、18世紀のイギリスの政治家エドマンド・バーク。彼は著書『フランス革命についての省察』の中で、フランス革命を厳しく批判しました。
フランス革命を主導している人たちは、人間の理性を間違いのないものだと考え、自分たちが正しさを所有し、その通りに社会を改造すれば、どんどん進歩して、必ずやいい社会になると言っていたんですね。
しかし、バークは理性を万能視する人間観に疑問を呈する。そんな完成可能な人間は果たしているのだろうか。どんなに頭がいい人でも愚かだし、間違えちゃうし、心の中にエゴややっかみはある。人間は誤謬(※1:ごびゅう)を含む、完成しきれない動物であると。
つまり、保守の思想では、「人間は間違えやすい」というのが前提にあるので、自分の発言も間違っているかもしれないという「自己懐疑の念」が常にあるのです。
だからこそ、「他者の言葉」と「歴史の知恵(=死者の言葉)」に耳を傾け、合意形成を図っていくというのが本来の保守の姿勢であり、これはリベラルマインドに非常に近い。

対局する二つのどちらかが正解ではなく、話し合って微調整を重ねながら、間にある無数の選択肢の中からバランスの取れた均衡点を探していく。リベラルの原点ともいえる、そういった保守的な寛容さが、何かを議論する時には大切だと思います。
小川:保守かリベラルか、みたいな二元論で捉えようとする考え方には、私も前から違うのでは、という思いを持っていました。
今の自民党をイメージすると、保守に対してあまりいいイメージを持たない人も多いですが、他者の立場を踏まえて、何が善なのか、間にあるものを探っていく寛容さが本来の保守のあるべき姿であり、その姿勢は、私が研究している文学や詩の言葉に多く見出すことができます。
ただ、現実問題として難しいのが、誰に対して、どう寛容であるべきなのかということ。たとえば、前述した女性ホームレスの話でも、人間関係、力の勾配、体調や気分など常に複雑な文脈があって、自由に生きているわけではなく、選ばされてる部分がある。
ということを踏まえると、ホームレスの人たちの生き方を尊重するのが寛容なのか、あるいはそうならないでいい社会を作るのが寛容なのか。寛容であるためには、どんな政治の仕組みを作っていけばいいのだろうか、いろいろな思考が巡ります。
文学が伝える、社会からこぼれ落ちる切実な声
中島:とても重要な視点ですね。
本来、保守の人たちは、人間は多様であり、そう簡単に分かち合うことはできないというのが前提にあるからこそ、何か一つのことを信じて、みんなで手を繋ごうという全体主義(※2)や共産主義(※3)的な社会は不可能だと考えるわけです。
保守の論客で、シェイクスピア作品の翻訳などをしていた福田恆存(ふくだ・つねあり)は戦後間もないころに『1匹と99匹と』というエッセイを執筆し、そこで彼は「人間が100匹の迷える子羊だとするならば、99匹を救おうとするのが政治である」と書いています。
つまり、どんなに再分配がうまくいき、ソーシャルインクルージョン(※4)が実現したとしても、孤独で死にたいと思ってしまう、“迷える最後の1匹”は必ず存在する。そして、その1匹を救う言葉を持っているのが文学であると。
このエッセイを通して福田は何を諌めようとしたのか。それは、100匹を救おうとする政治です。人の心をすべて包み込み、あらゆる苦悩から解放しようとする政治は、必ず全体主義のような暴力性を帯びてしまう。
それを避けるためには、文学こそが“迷える最後の1匹”を救わなくては、という使命感を持っていたのだと思います。前述したように、近代の人間観から排除されてきたケアなどはまさに文学が拾い上げてきたんじゃないかなと。
小川:2013年に亡くなるまでホームレスで暮らした小山さんという女性がノートに書き綴った言葉をまとめた『小山さんノート』(エトセトラブックス)という一冊があります。
日記ですが、『アンネの日記』と同じように文学でもあり、彼女は言葉を通して自分がどう生きているかを命に替えて表現しようとした人。
こんなに圧力がかかる現実を見るたびに、この心を侵されまい、侵されまいと密かに内なる部分を守ってきた。そんな魂を理解する国に行きたかった。
この叫びのような彼女の言葉は、生活が立ち行かなくなったときに手を差し伸べられる国ではない、そんな国に私たちは生きているんだということを切に伝えてくるんです。
政治が掴みきれない人間の現実、「こうやればこうなる」といった近代の理性的な理論だけではうまくいかない、こぼれ落ちてしまう領域って、文学にこそ綴られていると私も思います。
一方で、ジョージ・オーウェルの『1984』(※5)に代表されるようなディストピアを表現できるのも文学の力であり、文学は切実な言葉だけではなく、政治がその声を掴みきれなかったらこういうなるよという警鐘、その両方を届けようとしているんです。
以前、中島さんが新聞の論考で指摘されていたように、自民党政権が長く続いていることで日本は全体主義的な社会に変わってきていて、『1984』の世界に近づいている。権力者が既得権益を守ることに成功して、生の声をなきものとして政治をしているように感じます。
本当に必要な政治を探り当てるためには、文学にある本当に響かせなくてはいけない生の声を聞くことが今、必要とされているのではないでしょうか。
※1:誤謬|間違い。誤り。
※2:全体主義|個人の自由や人権よりも,国家の意思や利害を優先して統制する思想、政治体制。
※3:共産主義|財産を私有ではなく、共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。
※4:ソーシャルインクルージョン|誰も排除されることなく、すべての人が地域社会に参加する機会を持つこと。
※5:1984|1949年に刊行したイギリスの作家ジョージ・オーウェルのディストピアSF小説。物語の舞台は、1984年のオセアニアという国で、全体主義によって統治された近未来世界の恐怖、個人の自由と思想の重要性、そして権力による人間精神の破壊を描く。
illustration_Natsuki Kurachi text&Edit_Hinako Hase
▼後編はこちら
▼他連載記事はこちら

































