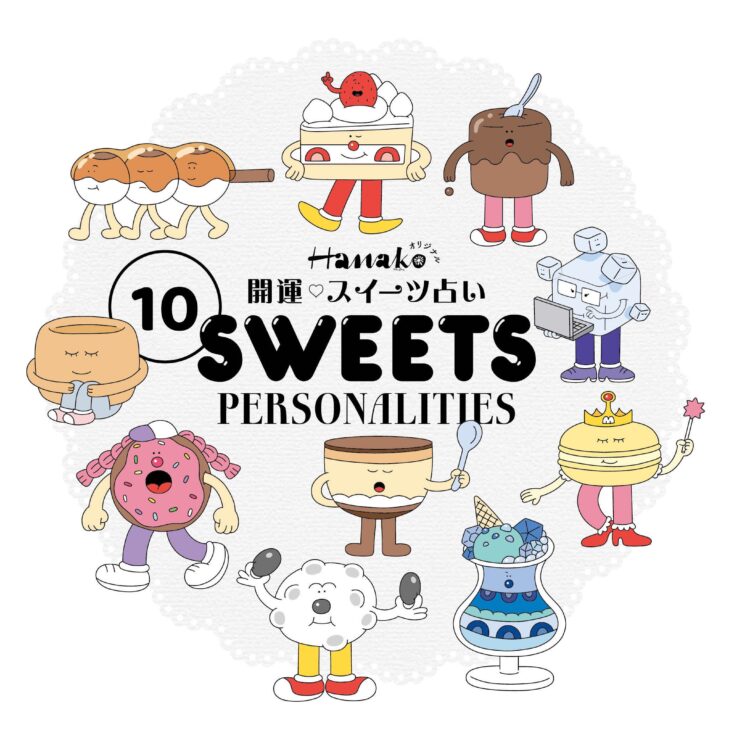開運担当歴16年ライターHのご利益道しるべ 【熊野】人知を越える力に触れて新たな私へ | 運気が上がる、私の参拝ルート #2
「開運」は誰もがもつ願い。運気をあげて前向きに溌剌と生きていきたいなら、ざわざわと物見遊山のついでではなく、心を鎮めて真っさらな気持ちで神さまのもとを訪れたいもの。自然にそんな心持ちになれるおすすめのルートを、開運担当歴16年のライターHがご紹介します。
豊かな自然に抱かれた紀伊半島の奥深く、山を超え谷を下りたどり着く熊野の聖地。その昔、京の都から遠く離れた熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社を詣でることは格別の功徳があるとされ、極楽往生を願う多くの人が訪れました。歴代の法王や上皇、女院など高貴な身分の人々から名もなき庶民まで、参詣する人々が列をなす様子を蟻の行列に例えて「蟻の熊野詣」という言葉も生まれたほど。
今も世界中から人を惹きつけてやまない熊野の地。その力に触れるには三社を詣るとともに、その一歩奥へと足を運ぶ必要があります。いざ、熊野信仰の起源となった磐座や滝、かつての巨大な中洲へ。古代の人々も畏敬の念を抱いた場に立てば、背筋が伸びて不思議と力が湧いてくるはず。

その一 川の流れに守られたかつての旧社地、大斎原へ

まずは熊野本宮大社へ詣でるなら、忘れてはならないのが旧社地である大斎原。かつてこの場所は熊野川、音無川、岩田川の合流に位置する巨大な中洲で、周囲を清らかな水に守られた結界でした。当時の境内は約1万1千坪。明治時代の大洪水で多くの社殿が流出して現在の場所に遷座するまで、川面に浮かぶ神域の森は特別な場だったのでしょう。今は2つの石祠を残すのみですが、大斎原の入り口に立つ大鳥居を見上げる時、自然の持つ大きな力を感じずにはおられません。
その二 那智御瀧に清められる

さらに熊野那智大社に詣でるなら、別宮 飛瀧神社は欠かせません。仁徳天皇の時代に熊野那智大社が造営されるまでは、現在の飛瀧神社の場所で御瀧の神と熊野の神々が祀られていました。飛瀧神社の御神体は那智御瀧そのもの。そのため神様を祀る社殿はなく、滝直下の拝所から那智御瀧を拝します。ここでは、延命長寿の水と伝わる滝壺の水に触れることも。
その三 巨大な磐座から熊野灘を一望する
そして熊野速玉大社まで足を運ぶなら、神倉神社は必須でしょう。権現山の麓から538段の急な石段を上った先、険しい崖に姿を現すのが御神体のゴトビキ岩。熊野の神が降り立ち鎮まったという磐座に、半ば潜り込むような形で社殿が設けられています。ゴトビキ岩の圧倒的な存在感と、熊野灘を広く遠く見渡す眺めは息を呑むほど。人知を超えた力を確信した古代の人々に、激しく共感。瑣末な日常など吹き飛んでしまいます。
その四 伊弉冉尊が眠る巨大な磐座を仰ぎ見る

写真AC
ゴトビキ岩と陰陽対をなすと言われるのが花の窟です。熊野灘に面した御神体の磐座は高さ約45メートル。火の神である軻遇突智尊を産んで命を落とした伊弉冉尊を葬った陵と伝わります。ここでも場の持つ力は圧倒的。太古の自然信仰が厳然と感じられる稀有な場所です。
その五 信仰の道、熊野古道のエネルギーも味方につける

写真提供 和歌山県観光連盟
熊野に張り巡らされた参詣道、熊野古道も、聖地を目指した多くの人々の想いが積み重なっています。自然の力と相まって、入口から少しの距離を歩くだけでも、力をもらえるような気がします。
熊野に行くなら三社をお参りするだけでなく、太古から続く自然信仰に触れられる場へ! 大地や森、水からエネルギーをもらって、運を開く力を身につけましょう。