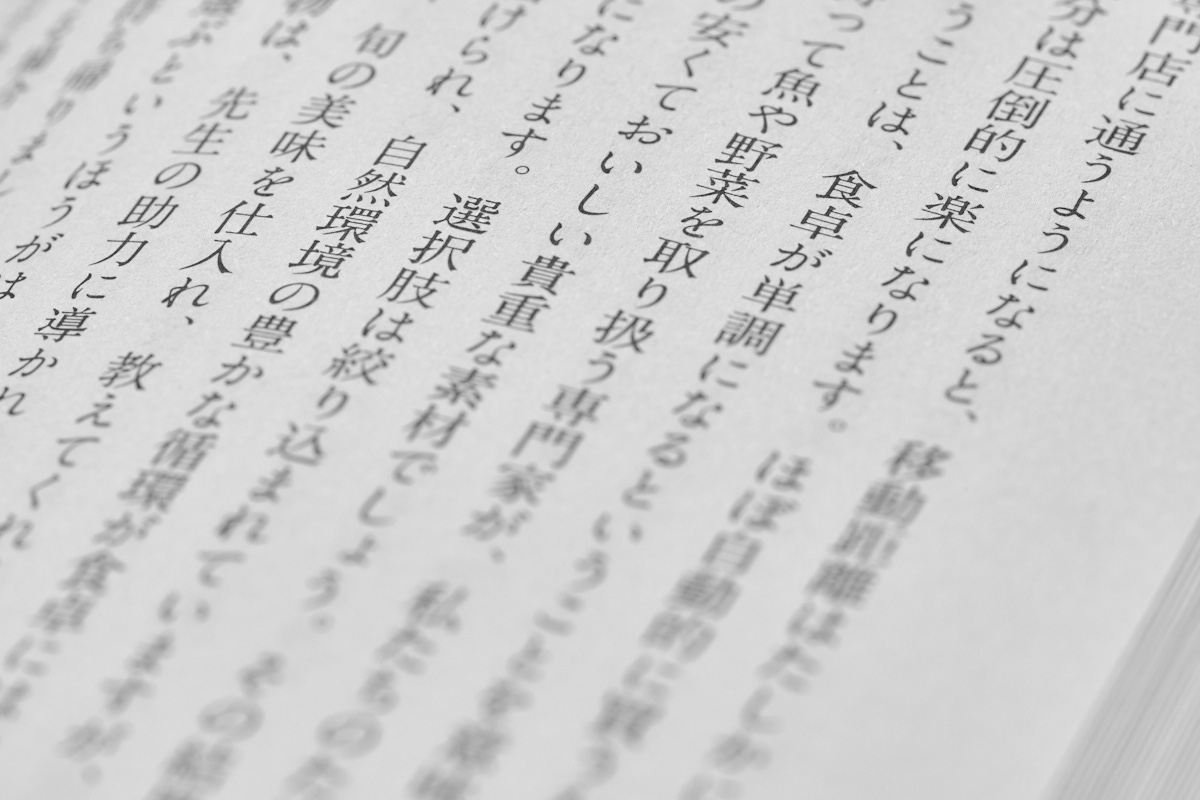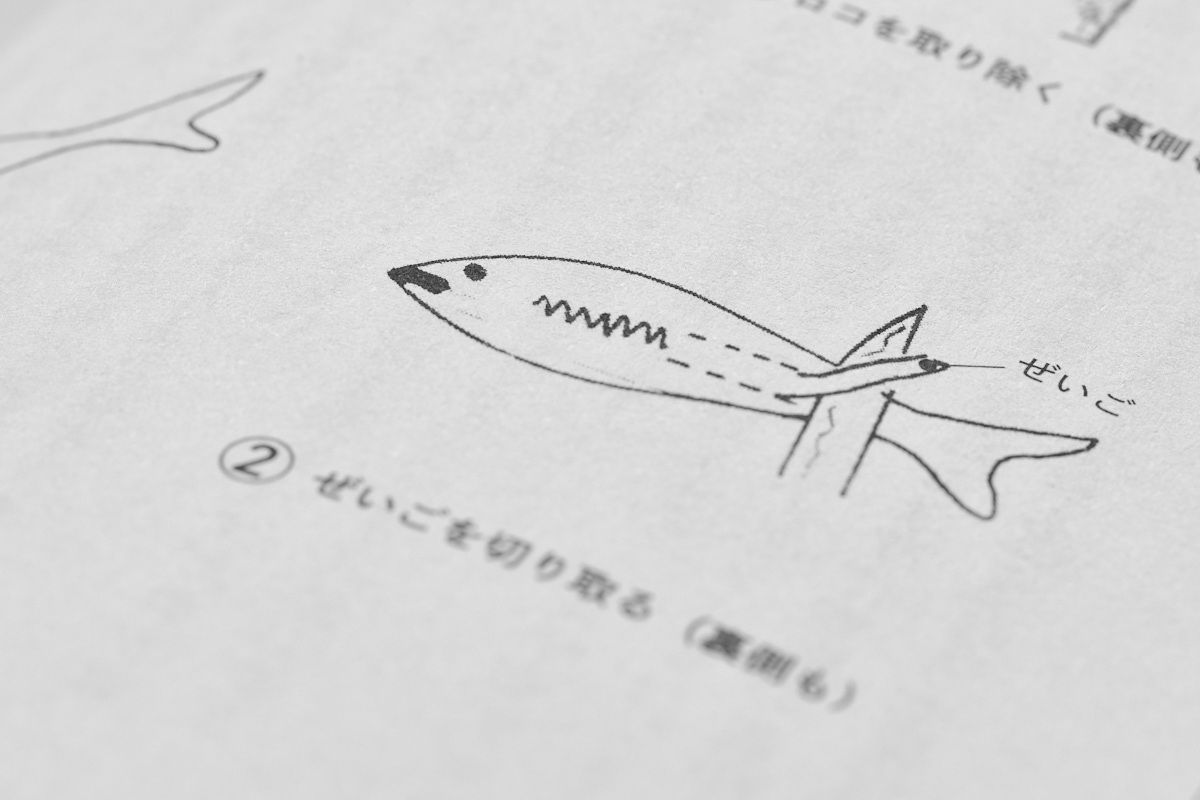きょうは、本を読みたいな #8 三浦哲哉『自炊者になるための26週』 | 生きる力を取り戻すレッスンとしての │
数時間、ときにもっと長い時間、一つのものに向き合い、その世界へと深く潜っていく。スマホで得られる情報もあるかもしれないけれど、本を長く、ゆっくり読んで考えないとたどりつけない視点や自分がある。たまにはスマホは隣の部屋にでも置いといて、静かにゆったり本を味わいましょう、本は心のデトックス。第8回目はメディア・コミュニティ「me and you little magazine & club」の野村由芽さんが『自炊者になるための26週』を紹介。
ここ数年、自炊をする機会が減っていた。やればいいじゃないか、やらなくて済むならいいのでは、と言われればどちらもその通りなのである。けれど、つくりたいという思いがあるのに、以前のようにつくることができず、自分を責めて、混乱していた。生きている心地を目減りさせている実感があった。そんなときに手にとった一冊が、三浦哲哉さんによる『自炊者になるための26週』だった。
目次をひとめみて、あ、おもしろそうだ、と引力にやられた。高揚感と、いまの自分にとって必要な本かもしれないという切実な予感。それらがないまぜになって、たちのぼる。
たとえば、こんな言葉が並んでいた。
“風味は映像である/においはへだたった時間を映す/青菜のおひたしは海のさざなみのように/目利きはするな/歌い継がれ愛されてきた民謡のような名レシピ/「ねばならぬ」ではなく/生活史を積分する”……
これはいったいなにについて書かれた本なのだろう? たしかに自分で選んだ本のはずなのに、一瞬、わからなくなった。それほどまでにこの本は、「料理についての本を読むぞ」という心づもりを軽々と飛び越える。ひろびろとした、そして胸のぎゅっとなる場所へと連れて行く。
「練習」を思わせるタイトルだけれど、手順のみを教えてレシピを覚えさせるような本ではない。著者のガイドのもと、「料理したくなる料理」をめざし、森のなかを一緒に探検しているような読み心地。目的地到達への鍵は、「風味の魅力」だ。
「風味の魅力」。それこそがすなわち「料理したくなる」秘密なのだけれど、これを解き明かす過程が、どきどきするほどおもしろい。小説家、哲学者、社会学者、精神科医……さまざまな専門家のテクストを踏まえた考察は、知的好奇心をくすぐられて頭のなかがぱちぱちと光る。けれど前のめりに読んでしまう理由はそれだけじゃない。じわじわと、元気になってゆく。自分の力が少しずつ戻ってくるような、自己回復の感覚。その芽生えをそっと撫でながら、確かめながら読み進めていく。
たとえば、第1章「おいしいトーストの焼き方」のこんなくだり。“毎朝焼くトーストにも、しみじみと感動することはありえます”と、読者を誘う。続いて、においがやってくる。“ひとを恍惚とさせるトースト”というのは“いいにおいのする熱々の湯気を、パンに充満させること”。これなら、できそう。
「簡単そう」だけど、「意外」。時間がなかったり、疲れていたりしたとしても「これならできるのでは?」とか「むむ、やってみたいな」という気を起こさせる仕掛けが、この本のあちこちに散りばめられている。それがとても心強くてすきだ。「自分にもできるかもしれない」というちいさな期待の芽は、ものごとをはじめてみる気力につながるし、明日を生きていくのが少し楽しみになるから。
と、やる気が出てきたところで、一見逆のような言葉が目に飛び込んできた。「目利きはするな」。専門家でも目利きは難しいのだから、店主がいいものを選んでくれるお店を知っていれば、そもそも目利きをする必要はないと書かれている。魚屋、肉屋、パン屋、ワイン屋……専門店の主におすすめを聞けば、“買い物をする気分は圧倒的に楽になり”“ほぼ自動的に買うものが決まる”と続く。すると、旬のおいしさが安く手に入り、数ある選択肢からおすすめが絞られる、自炊ハードルが下がるというのだ。
それぞれの持ち場で営みを続けてきた人の声を聞く。旬の足音を聞くーー。これはつまり、自炊にも「耳を澄ませる」ことが大切だということではないだろうか。わたしにとって、本書の魅力のひとつは「自己回復」だと書いたけれど、そこにあるのはすべてを自分だけで解決しようとする態度ではないし、無数のひとりひとりの寄り集まった世界ではそもそも無理な話だ。
他者や世界へ、自分の感覚を今より少しひらいてみる。鼻だけではなく、目や耳や心も。すると、至るところに実はすでにある豊かな風味が、五感を通してわたしのもとに届く。手紙を受けとるみたいにして。自分とは異なる他者とのまじわりは、ときに痛みももたらすけれど、ふるえるような輝きももたらす。風味によって、生きているなあ、という心地のする出会いを体験することができる。
自炊が、生きることの心の深い部分を支えるというのは、この本の重要なテーマである「風味は映像である」という内容ともかかわってくる。自分でだしを取ってつくる、味噌汁のくだりから引用する。
“だしを抽出するときの小鍋の中には、こんぶとさかながいるので海の借景ともいえます。海とのつながりが意識されていて、水中花のようでもあり、そこで香りが蘇るというわけです”
料理とは、風味によって「いまここにいながら、遠くの空間や時間を映す」もの。映像批評、研究、表象文化論の研究者として活動する著者ゆえの厚みのある説得力をもって、わたしたちの台所を、食卓を、映画館のスクリーンに一変させる。そして最後、これまで料理のほうを向いていた光は、わたしたちひとりひとりを照らしはじめる。
“同じ風味に出会ったとして、そのどんな索引から何を検索するかは、そのひとの人生の履歴によります”
つまりこういうことが書かれているのだとわたしは受け取った。風味のルーツを辿るとき、産地や作り手、文化、伝統的な由来などを尊重する気持ちを忘れないでいることが大切だ。けれど同時に、この本は、風味に出会ったときに呼び覚まされる、一人ひとりの記憶や思い出、感じ方のようなものを肯定する。わたしの「経験」と「履歴」は、他のひとのそれとは決して取り替えることのできない個性という「地」になって、料理とわたしが出会う度に、一回性の風景がその都度映し出される。たとえばそれはーー旅立った祖母が「これがすきやきだ」と言いながらつくってくれたごった煮かもしれないし、バスを待っている間に見知らぬ人からもらった2粒のチョコレートーーかもしれない、そんな個人的な風景も混ざり合う。
風味が運ぶ、「世界の消息」。風味が呼び覚ます、折り畳まれていた「わたしの記憶」。風味の宿った料理の前では両者が出会い、まるで自分のためだけにつくられた映画のようなものが上映される。そこには受け取り手の生が反映されてしまう。まぎれもない、ひとりひとりの複雑な生の肯定だと思う。
この本を読みながら、思い出した記憶がいくつもあった。働きはじめの頃、せめてもの創造性が自分のなかに残っていると証明したくて深夜2時から煮込んだ「スープ」作りの日課。おやつに食べた儚そうなわらび餅が喉につまった「鎌倉」の海辺のデート。初めての「サラダうどん」を家族全員で食べた地元の夏、夏という季節は子ども時代のすべてに似ているなと思ったこと。
これは、本の紹介とは関係のない個人的な思い出の断片だ。けれどこんなふうに、自分のためにしか語る必要のない記憶を思い出す行為が、自分を癒すことがあると、この本を読めばちゃんとわかる。
ここ数年のコロナの状況は自分の心身にも侵食し、未知の偶然や他者を招き入れるような余白のない、閉塞感のある日々だった。だからこそ、五感をひらいて世界とかかわり、些細な思い出のこまごまとつまった引き出しを開けて、自分のためだけに思い出しながら、料理をつくってみたい。
『自炊者になるための26週』を読んでから、いくつもの料理を自分でつくった。わたしだけの、あなただけの人生があるから、感じとれる予感や、思い出せる記憶があって、それは決して無駄ななにかではなく、いまここにいることを支え、これからにつながっていく生の証だと、なんだか勇気づけられた。料理の本でもあるけれど、自己回復への回路を増やす本でもある。これはそんな、生きる力を取り戻すレッスンのような一冊だ。
『自炊者になるための26週』
さっと買って、さっと作って、この上なく幸福になれる。「トーストを焼くだけ」からはじまる、日々の小さな創造行為。“ほぼ毎日キッチンに立つ”映画研究者が、その手立てを具体的に語った、おいしさと創造力をめぐる、全くあたらしい理論&実践の自炊書。2,178円(朝日出版社)