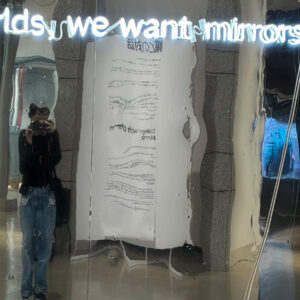「手作りの夢、手作りの豚、手作りの今日」 ――北鎌倉・たからの庭・窯で蚊取り豚づくり体験 | 児玉雨子のKANAGAWA探訪#11
神奈川県出身の小説家・児玉雨子さんの地元探訪記。今回は初夏の鎌倉で陶芸体験の巻。JR北鎌倉駅から徒歩10分の場所にある古民家アトリエ「たからの庭」で陶芸作家の先生の指南を受けながら、来る猛暑に向けて「蚊取り豚」をつくってみました。
たからの庭/たからの窯
鎌倉市山ノ内1418-ロ
*JR横須賀線「北鎌倉」駅 徒歩10分
https://www.takaranokama.com/
ここ一年ほどちょこちょこと陶芸やクラフト体験を探しては参加している。こういったら語弊しかないのだが、ホストクラブやコンカフェの初回荒らしならぬ、クラフト体験荒らしといったところだろうか(荒らせるほどの技術もないのだが……)。ようやく遊びと仕事のスケジュール調整の要領を掴めてきたような気もしていて、もっといろんなところに行かなきゃ! となかば躍起になって遊んでいるのだ。顧みてみれば特にここ数年はコロナ禍もあってずっと引きこもっていて、それにストレスを感じているつもりはないつもりだった。けれどやはり、今ここまで元気に動き回っているのなら、何かしら塞ぎ込んでいたものがあったのかもしれない。
仕事か何かの移動中に漫然とGoogleマップウォッチングをしていると、北鎌倉の浄智寺の近くに村のようなものを見つけた。「たからの庭」というシェアアトリエで、予約制で茶室、陶芸、料理、自然体験などができる施設を擁しているらしい。その中の「たからの窯」ではさまざまな陶芸体験教室が開かれているそうなので、さっそく予約をして、その週末に北鎌倉へ飛んでいった。


初夏の週末の北鎌倉駅は観光客が多かった……という表現もどうなんだろうか。「観光客が多い」街の様相もすでに日常になってきたし、むしろ今までが単一民族社会だっただけのような。神社仏閣に黄色人種以外のひとがいることにどうのこうの言うのって「ラーメン屋に女・子供がひとりで入っている!」と騒いでいるみたいなんだよなぁ……などと考えながら歩道を進むこと約10分、浄智寺に入るゆるやかな坂道を見つける。

新緑のまぶしい境内には入らず、その左脇の道をしばらく進むとたからの庭の入り口が右手に見える。私の前をさわやかな夏着物を召された女性二人が歩き、ときどき立ち止まっては写真を撮っていた。どうやらこの日は茶室では茶会もやっているらしい。しゃらんしゃらんと音が鳴るような美しい背筋に感化され、猫背で息を切らせていた私も顎を引いてぴんと姿勢を正してみる。二人は手前の茶室に入り、私はより奥へ奥へと進む。木道を渡り、むわむわと立つ草いきれをかき分けながら小さな坂をのぼると、窯の煙突と畑と古民家がぱっとこちらを見下ろしてくる。すっかり猫背に戻っていた。


予約した時間通りに庭の最奥の窯に入ると、陶芸作家でたからの窯店長の渡邉庸子先生がすでに二人の電動ろくろ体験中のお客さんの対応をしていた。私はアトリエの入り口付近にぽつねんと置かれているひとり用の机に通してもらい、板のような粘土を前に、もくもくと作品発送時のための送り状に情報を記入する。電動ろくろの人たちの合間に、粘土の取り扱い方法や、今日作る蚊取り豚の胴体の構造を指導してもらう。

まずは板のように整えられた粘土を筒型に巻き、隙間を指で馴染ませる。文字にすればこんなに単純な工程でも、空気が入らないよう、筒がずれないようにするだけでも一苦労だ。そういえば、私は昔から指先が不器用で折り紙をピンと尖らせるように二つに折ることができず、幼稚園のころにしっかり者の女の子にどうしてそんなに下手なのかとなじられながら折り紙を折った苦い思い出がある。案の定筒は少しずれてしまったが、これも「味」と自分に言い聞かせる。

アトリエ中央の長机に、新たな二人組のお客さんがやってくる。このたからの窯では電動ろくろや手びねり体験だけでなく、この庭で採取できる季節の植物を押して模様を作る「葉っぱの器づくり」ができる。二人はそれを予約していたようだ。先生から説明を受けてから、二人はお皿に押すための植物を採取しに再び席を立った。
先生は最初からいた電動ろくろの二人組のようすを見に行ったかと思えば、また新しくやってきたグループ客の対応をして忙しそうだ。と、私がのんきな気持ちで粘土をちまちまといじっていると「おや、ちょっとだけずれましたね。問題ないですけどね」と言って目の前に先生が音もなくやってきて立っている。風通しはいいもののあまりエアコンを効かせていないアトリエの中、汗ひとつかかず同時並行で多くのお客さんを次々さばいてゆく、その辣腕さ!
まっすぐに巻けなかった粘土の端を手早く修正しながら「そしたら足を作りましょうか」と見本の蚊取りブタをひっくり返して見せ、適当に粘土をちぎって手のひらの中で蹄のある豚の足を一本成形してしまった。この間、ものの数秒。先生の手もとは素早いのに、スローモーション。千手観音のようにすべてのコマが見えるから不思議だ。
先生の見よう見まねで豚の足を作り始めてみる。一見簡単そうなのに、自分で作ろうとすると脚の形がまとまらない。長靴のような形になる。長靴を履いた豚もかわいいけど、今回はとりあえず先生の見本に近づけたい! と見本の蹄を観察したり、スマホで豚の足を調べてみたりして試行錯誤してみる。
そのあとしばらく作業に集中していて気づかなかったけれど、ふと顔を上げるとアトリエは大盛況だった。というか、明らかに用意された作業用机の数を超えて人が溢れている。どうやら予約フォームのエラーで先生に予約者の通知が届いておらず、想定していたよりも多くお客さんが来てしまっていたらしい。冷静沈着でてきぱきとしている先生でもさすがにほんのすこし慌てているようすだった。
てんやわんやの状況にもかかわらずこちらのことも忘れず気にかけてくださった先生に、思わず「あとは勝手に作ります」といった雰囲気を放ち、私は押し黙って他のパーツも作り始めてしまう。さながら、大人がある程度放っておいても大丈夫な子だ。まぁ、電動ろくろのように緊張感を持つものではなかったし、最近はこういう状況に差し当たることってこのごろあまりなかったなぁと、妙にしみじみともしていた。空気が入らないように気をつけてくださいね、と注意しながら、先生は新しいお客さんの元へふたたび瞬間移動していった。

粘土をこねながら、辺りを見回した。中央の長机に座って待っていた母娘の二人組に、先生が新しい粘土と作業台を用意しながら「何を作りたいですか?」と質問した。どうやらこの母娘の予約もエラーで弾かれていて、先生は二人が何を作りに来たのか把握しきれていなかったようだ。
「お皿なんですけど」と母親が答えると、先生は「丸い平皿ですか?四角い角皿ですか?」と質問を進めた。円形の皿と角皿とでは作り方が異なるので、そこははっきりと決めて取りかからなければならないらしい。母親は答えに詰まって「魚の皿なんですけれど、どっちでしょうか?」と返した。きっと角皿なんだろうな。私は視線を手元の粘土に戻してなんとなくそう予想していると、先生は彼女を責めるでも呆れるでもなく、しかし毅然とした声色でこうおっしゃった。
「どんなお皿でも、あなたが魚を乗せれば、平皿でも角皿でもそれは〈魚の皿〉になりますよ」
これはなんだか私の元にも言葉が転がってきて、粘土をいじる手が止まった。こうして改めて考えればそりゃそうだと納得するのだが、私も無意識に魚は長方形の四角い角皿だと決めてかかっていたことを覚って、アトリエの端っこで小さなコペルニクス的転回をひとりで感じていた。

昨年だろうか、友達と初めて電動ろくろ陶芸体験に行ったとき、はじめに「創作に失敗はない、そういうものになっただけ、作りたいものを作りましょう」とスタッフさんに宣言されたのを思い出す。こんなにも自明のことでも、心の深いところまでその言葉が染みこんで、そのまま私の中で結晶になって光っているのだ。
我ながら何をいっちょまえにさ、と思うけれど、ありがたいことに作詞や小説やエッセイを発表する場に恵まれているうちに、やはり私の中にも「こうしなければならない」というつまらない模範解答が出来上がってきていた。そういった凝り固まった型は、納得しないまま繰り返されるリテイク、批評、もしくは中傷に堪えうるために私自身が仕上げたひとつの鎧でもあった。こういったクラフト初回体験荒らしは、その鎧を脱ぎ捨ててやわらかく傷つきやすい肉の塊のまま、作りたい何かを思うがままに作りだす、ということを私が少しずつ取り戻そうとしたくてやっているのかもしれない。たとえそうじゃなくても楽しいから、まぁいっか。

魚の皿の話で、ますますうろたえていたお客さんの表情を見て、先生は「まぁ、もしあまり陶芸の経験ながければ、最初は丸い平皿がいいかもしれませんね」とやさしく道筋を立ててフォローされていた。自由に感動しつつ、たしかに、思うがままの自由って結構果てしなくて、途方に暮れてしまうかもなぁ。先生は自由に作りたいひとの気持ちを尊重しつつ、自由すぎると困るひとへのアシストもさりげなかった。

それから数十分かけて真珠を身につけた豚の成形を終えた。乾燥と焼きと発送の手続きをすべての工程と合わせると、手元に届くのは一・五~二ヶ月後ほどになるらしい。この蚊取り豚は包んだ藁の燃え方で模様がつくそうで、その偶然性も楽しみ。
そのあとはしばらくたからの庭を散策し、帰りしなには浄智寺にも立ち寄った。せっかく北鎌倉に来たのなら、といろいろと行ってみたけれど、やっぱり魚の皿のことが一日中は頭の中できらめきながら巡り続けていて、そのことばかり思い出す。