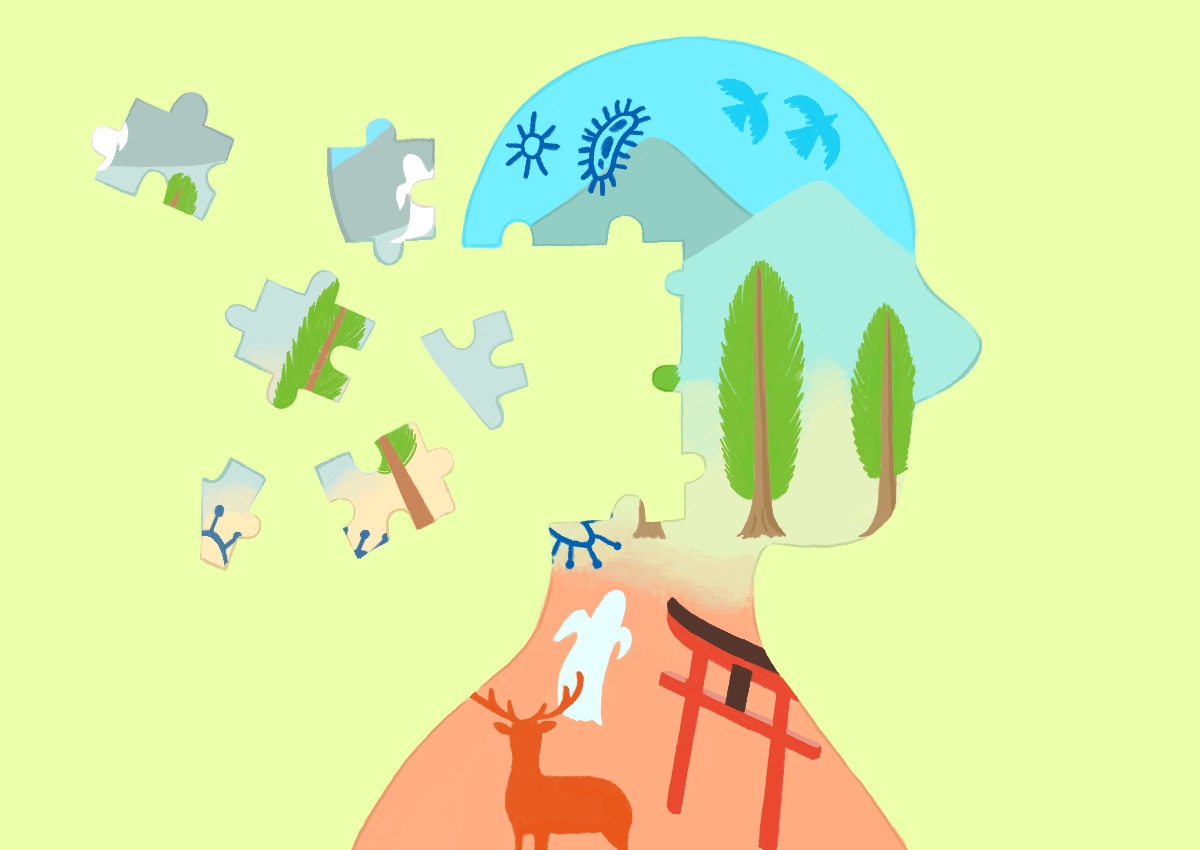【武田砂鉄×頭木弘樹】蟻の視点、持ってる? マナーに厳しい今の社会で、“ためらい”や“曖昧さ”を持つ大切さ

※記事のスクショをSNSやWebページ上に掲載する行為は、著作権法違反、肖像権侵害、名誉毀損罪・侮辱罪に該当し、場合によっては法的責任を問われる可能性があります。
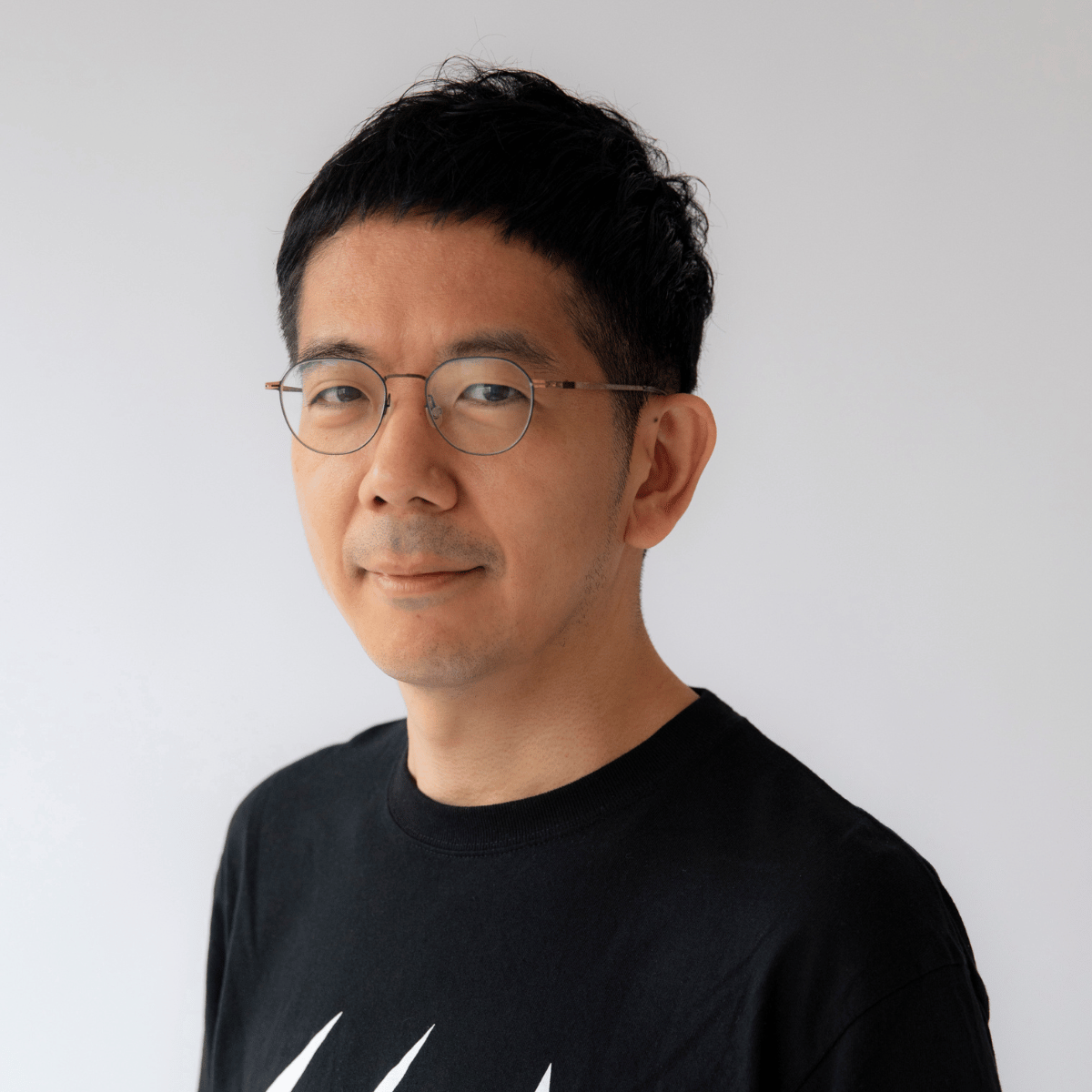
出版社勤務を経て、2014年よりフリーライターに。2015年『紋切型社会』(新潮文庫)でBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。週刊誌、文芸誌、ファッション誌、ウェブメディアなど、さまざまな媒体で連載を執筆するほか、近年はラジオパーソナリティとしても活動の幅を広げている。近著に『わかりやすさの罪』(朝日文庫)、『マチズモを削り取れ』(集英社文庫)、『テレビ磁石』(光文社)など。

大学在学中の20歳で難病である「難病潰瘍性大腸炎」と診断され、13年に及ぶ闘病生活を送る。そのときにフランツ・カフカの著作をはじめ、読書に救われた経験から『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を編訳。近著に『自分疲れ ココロとカラダのあいだ』(創元社)、『決定版カフカ短編集』『カフカ断片集』(いずれも新潮社)、『口の立つやつが勝つってことでいいのか』(青土社)など。
▼前編はこちら
マナーに厳しい社会は危険…?
武田砂鉄さん(以下、武田):前編では、アメリカの現状から、“多様性”を取り巻く環境について考えました。そのなかで、誰しも弱さを抱えているにもかかわらず、依然として社会の中では強いことがよしとされているがために、強い側に固執してしまう傾向があるという話が出てきました。
頭木さんの著書『口が立つやつが勝つってことでいいのか』(青土社)のなかで、映画『火垂るの墓』を見た人がSNSで「感謝の気持ちが足りない」といった趣旨のコメントをして話題になったというエピソードがありましたね。
このエピソードが象徴するように、“弱い”立場に置かれ、しんどい思いをしている人たちに向かって、「何かを嘆願するのであれば、気持ちの表し方があるだろう」と言わんばかりに、“口の立つ強者”に権利を求めるには、それなりの言葉や行動で示すべきという空気がマジョリティの人々のなかで強くなっているのを感じます。
これも、強い側でありたいという思いの裏返しなのかなと思ったり。
頭木弘樹さん(以下、頭木):感謝ってエスカレートしていくと怖いんですよね。前編でも触れたように、私は以前、宮古島へ移住した経験があり、そのときはじめてお礼を言わない世界を体験しました。
宮古島では親切にするのが当たり前で、お礼を言わないのが当たり前だから、相手が恐縮せず、どんどん親切にできるし、他者の親切を素直に受け入れられるようになる。これって素晴らしいことだなと思いました。
武田:東京で暮らしていると、「ありがとう」「すみません」しか言っていないみたいな半日もありますからね(笑)。
しかもそれは本質的には「ありがとう」というより、態度を明確に示しておかないと、相手に別の感情を勝手に受け取られるかもしれないという、ある種の義務感みたいなものからきていますよね。
頭木:マナーに厳しいって、危険な兆候だなと思います。それこそ宮古島で、郵便局の職員に土下座をさせたナイチャー(本土出身の人を指す、沖縄の方言)がいたんです。
そのとき「これだから、ナイチャーは」というひと括りの集団にされちゃうかもしれないということへの恐怖を感じました。
宮古島にはそんなことをする人おそらくいないので、「ナイチャーをすべて排除してしまえば、そんなことは起きなくなる」と思ってしまうのも理解できるし、差別問題の根底にはこういった感覚が横たわっているのかなと納得する部分がありました。
武田:書店に“ヘイト本”が並び、ネットに〇〇人は〜だという言葉が溢れている時期もありましたが、これは日本人の不安の写し鏡のように感じています。
他者を否定することで、自分はまだまっとうなんだと思いたいという表れなのかなと。何かのせいにすればひとまず自分は安心できるという動きはSNSをはじめ、今も形や角度を変えて、ずっと起き続けています。
いつやるの? 今じゃない。もっと、ひと呼吸のためらいを
頭木:日本人であるというのは変わらないから、そこにすがっておけば、安心できるのかもしできるのかもしれません。
昨今は、インターネットのおかげで離れていても同じ考え同士で集団を作りやすく、集団間の分断が激しくなっている印象を受けます。私自身は病気で引きこもっていたときは、インターネットが救いでした。
しかし、本来は多様な出会いやつながりを作ってくれるはずだったインターネットが、現在は一様な集団が分裂するという状況を作り出しているのは残念です。
武田:人間には何かの集団に帰属して生きたいという心理があると思います。ただ、これまではそれなりに時間をかけて集団を築いていっていたのに、インターネットにより集団化のスピードが早くなっていて、本当にこれでいいんだろうかと悩む時間がなくなっていますよね。
予備校講師の林修さんの「いつやるの? 今でしょ!」というキャッチコピーが流行しましたが、私はそうではなく「いつやるの? 今じゃない!」を広めたいなと思っています(笑)。
受験勉強は確かに今やったほうがいいかもしれませんが、世の中全体が「今でしょ!」という雰囲気になっていて、「いつやるの?」と聞かれても、とりあえず“ひと呼吸置く”ということを思考のベースに持つのは大切なんじゃないかなと。
頭木:そのフレーズ、いいですね(笑)。前編でも登場した山田太一先生は、中学時代の先生に「『〜だとしたら』っていう考え方をしなさい」と言われたとおっしゃっていて、それを生涯、実践されていました。
何事もけっして断定しない。「こうだとしたらこうだろう。だとしたら、こうじゃなければこうじゃないかもしれない」と保留つきですべての物事を考える。それって、相当大変だと思うのですが、日常でも実践されていました。
武田:たぶん、今の会話のテクニック本で一番“やめるべき”とされている類のことだと思うのですが、今、一番大事なことではないでしょうか。
担当しているラジオ番組でも、ひとつの社会問題についていろいろと話したあとに最後に「引き続き考えていくしかないですね」みたいなことを言いがちで、それは本当に引き続き考えていくしかないからなんですが、「逃げているだろう」と思う人も割と多いようなんです。
頭木:もっと断定してほしいんですよね。でも、“ためらいを持つ”ってすごく大切。
例えば目の前に自分にとって不愉快なことをしている人がいたら、「自分ならこんなことしない」と怒りが湧くと思うのですが、その人=悪と決めつける前に「何か特別な事情があるのかもしれない」と想像すると怒りも和らぎますよね。
以前、電車で足を大きく開いて座っていた中年男性の足を、「なんて嫌なヤツだ!」といった調子で蹴った人を見たのですが、股関節の問題などが原因で開いてしか座れない人もいる。“ためらう間”がないと、過激な行動にでてしまいがちです。
武田:とはいえ、前編でも触れたように、トランプ大統領のような断定的で、切り捨てを厭わない態度へ爽快感を感じている人が多いと思うと、“曖昧さ”や“ためらい”の重要性を広げていくのはなかなか難しいですよね。
弱さを生かすことのできる社会は強い
頭木:怖いのは切り捨てが起きたとき、被害を受けないマジョリティ側の人は「自分は被害を受けない集団でよかった」という安心感を感じると思うこと。
明日は我が身と言いますが、そう言われると「いや、そんなことはない」と逆に反発が強まるんです。病気など当たり前が崩壊するような経験をしている人でなければ、誰しもが漠然とした英雄感を持っていて、「自分は違う」と思ってしまうところはありますよね。
武田:前述の頭木さんの著書で、自然動物番組でアリクイが蟻を食べているシーンを見て、蟻の気持ちを想像していて、一緒に見ていた人と見方が全然違ったと書かれていたのが印象的でした。

頭木:闘病経験をして見方が大きく変わりましたね。昔はアリクイ側の気持ちを想像していたのですが、今は食べられる側のリアリティを想像してしまいます。
武田:“多様性疲れ”が広がる今の社会は「蟻の気持ちなんてもうよくないか?」みたいな感覚に近いのでしょうか。私は現状、アリクイ側の人間かもしれませんが、蟻のことを想像し続けることは諦めたくないと常々思っています。
頭木:小説家の安部公房(※1)が、「弱者をどれだけ抱え込めるかが文化レベルだ」といった趣旨のことを言っています。
例えば、寒さに弱い人がいるからセーターが生まれたように、弱者がいるほど文明は進むし、弱者をどれだけ生かすことができるかということが文化レベルを表すということで、なるほどなあと思いました。
多くの人は強くありたがりますが、弱い人の声を大切に拾い上げ、生かしていったほうが、社会全体が強くなり、実はすべての人にとってメリットがあるんですよね。でも、そういった長期的な視点が現在は抜け落ちてしまっているように思います。
傷つけることを恐れすぎずない。弱さを通してつながりを紡いでいく
武田:今月の売上につながらないことは切り捨てる、今はそんな社会ですよね。誰しもが現代社会では、ゴール達成目的ありきで行動しがちですが、そうでないあり方を教えてくれたのが高校時代の友人I君です。
I君は一緒に帰っていると急に走り出して「どうしたの?」と聞いたら、「あの角に鈴木亜美(※2)がいる“かもしれない”と思ったんだ」って言ったんですね(笑)。
私はそこに鈴木亜美らしき人がいたり、「いるよ」と言われたり、その可能性が高いということを把握したら走り出したと思うんです。でも、I君は「そんな気がした」って走り出したんです。
それと同様、我々は何か目印や情報がないと走らない。でも、I君のような明確なゴールなんて目の前になくても走っていってしまうような感覚がこれからの社会では必要なのかな。
昨今、よく言われるアルゴリズムで私たちの手元には選別されて最適化された情報しか届かないですよね。でもあえて、アルゴリズムが予想できないようなまったく関係ないことをしてみる。その延長線上に多様な選択肢があるのではと思いたいです。
頭木:目的なしに走っていく人生のほうが絶対楽しいんですよね(笑)。それと同じで多様性もメリットありきで既定路線でものを考えると「面倒くさい」と思ってしまいがち。そのものをおもしろいと楽しむ感覚が必要なのではないでしょうか。
その点、前編でも言ったようにマイノリティ側の人が「もっと勉強してください」っていうのは無理があるし、“多様性疲れ”を助長してしまうと思います。
では、多様性に強いってどういう人かっていったら、目の前にいる人に向き合って話を聞いて素直に受け止める人だと思います。エビアレルギーですと言ったら、エビは出さないじゃないですか。それと同じですよね。
武田:今はエビアレルギーと言うと、「君はエビアレルギーの歴史を知っているのか」と言われるか、「口の中に突っ込めば食べられるだろう」と暴力的なことをされかねないですよね。
だから、誠実な人ほど、下手なことを言って相手を傷つけないように、遠巻きになって黙ってしまう。エビアレルギーについてよく知らないから語るのをやめようとなってしまうわけです。
頭木:遠巻きになってしまった人に戻ってきてもらうには、「傷つけてもいいし、間違えてもいい」という前提を共有することが必要なのかなと思います。
もちろん故意的に傷つけたりするのはよくないですが、人間関係で意図せず誰かを傷つけてしまうのは避けがたい。
武田:傷つけてはいけないというスローガン自体はとてもいいことだからこそ、そのシフトチェンジをしていくのがまた難しいですよね。
頭木:そこに多様性という複雑で多様な要素が加わるとなおさらで。でも、私は大切なのは“傷つけ続けない”ということだと思います。
武田:相手との関係値やさまざまな文脈があるなかで、自分のふとした言動や態度が知らぬ間に誰かを傷つけてしまう可能性を完全には排除できなくて、どこでどうナイフに変化しているかわかないことへの恐怖は日々感じていますね。
頭木:こういうもののバランス、適正値を決めるのは難しいですよね。そこはやっぱり長期的に自然と調整されていくものだとは思うのですが、長期的な目線を持てない今は本当に難しい問題。
“多様性疲れ”で離れていってしまった人にもう一度振り向いてもらうのには、あらゆる角度で誰しもが持ちうるマイノリティ性から共通点を見出し、横のつながりを築くことが大切な気がします。
持病を持つ私は女性のフェミニズム運動は共感したり、救われたりする部分が多いんです。それと同じように、マイノリティ同士のつながりはもちろん、自分とは関係ないと思っているようなことでも、マイノリティの悩みが改善されることは誰かの行きやすさにつながる可能性があるわけです。
武田:今は何でもカテゴリー分けが進んでいますが、その橋渡しをする糸がないがしろにされている部分がありますよね。そこにもっと意識を向け、その細い糸を少しずつ紡いでいくという感覚を持っていかないといけない。そこに、多様性に疲れた社会を次のフェーズへと引き上げる可能性があるのかもしれません。
※1:安部公房|小説家、劇作家、演出家。昭和中期から平成初期にかけて活躍した現代日本文学を代表する作家の一人。ノーベル文学賞候補として世界的にも高い評価を受けた。
※2:鈴木亜美|歌手、女優。オーディションバラエティ〈ASAYAN〉(テレビ東京) を経て、小室哲哉プロデュースで1998年「love the island」で歌手デビュー。女優としても数々のドラマや映画に出演。
illustration_Natsuki Kurachi text&Edit_Hinako Hase