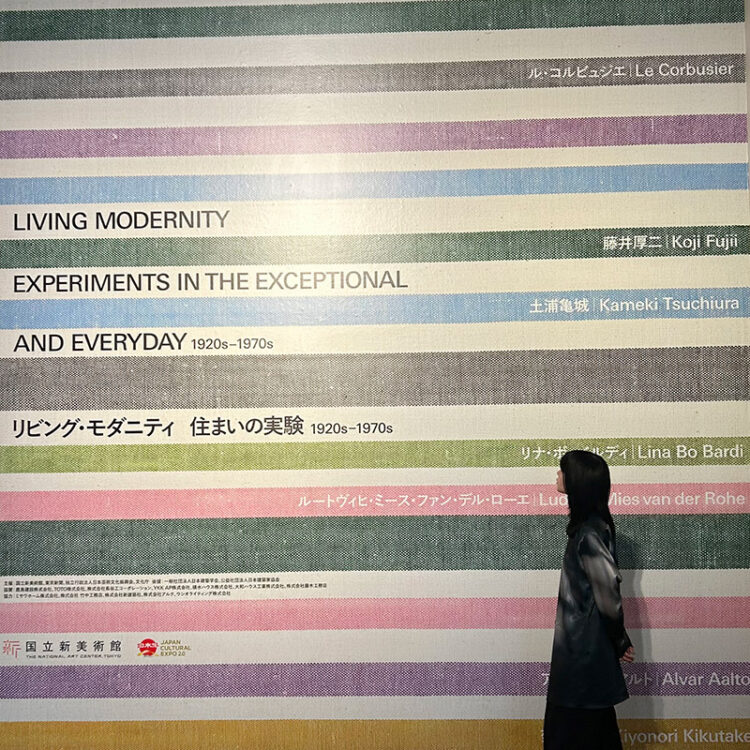苅田梨都子の東京アート訪問記# 13 もう行った?『ポール・ケアホルム展』パナソニック汐留美術館
ファッションデザイナー・苅田梨都子さんが気になる美術展に足を運び、そこでの体験を写真とテキストで綴るコラム連載です。第13回目は、パナソニック汐留美術館で開催中の『ポール・ケアホルム展』へ。
今回は新橋・汐留にあるパナソニック汐留美術館で現在開催中の『ポール・ケアホルム展』へ訪れる。
直近だと、2022年に東京都美術館で開催していた『フィン・ユールとデンマークの椅子』展へ訪れた記憶と今回の展示が結びつく。
再び“椅子”という日常生活にとって身近な道具でもあり家具である造形物に着目する機会を得て、純粋にワクワクしながら展示会場へ足を運ぶ。
ポール・ケアホルム(1929 - 1980)は、20世紀デンマークを代表する家具デザイナーである。本展ではポール・ケアホルムの主要作品を網羅した、日本の美術館では初めての展覧会となる。
ケアホルムの作品の特徴は、石や金属などの硬質な素材を取り合わせた厳格なデザイン。それでいて、決して冷たい印象を与えず、日本の建築や空間にも相性が良く、愛好家の中でも知る人ぞ知るデザイナーとして根強く支持されているそうだ。
本展の会場は大きく分けて三つの章で構成されている。こちらの壁や床がベージュのエリアは第一章で、ケアホルム自身についての年譜や写真などのにより20世紀デンマークデザインの系譜におけるケアホルムの位置づけを概説している。

ポール・ケアホルムの代表作の一つとして、画像1枚目に写っているエレメントチェア《PK 25》がある。
コペンハーゲン美術工芸学校の卒業制作としてデザインしたものだそう。
この椅子のフレームは1枚の大きな鉄板に切り込みを入れ立体的なフレームに曲げられ、そこに非常に強いロープを結びつけて完成する。
説明を聞いた際、無駄のないデザインで男性的要素を感じさせられた。そして、椅子は強度も非常に大切であり、その点で工夫がデザインの中に落とし込まれているのだと捉えた。
私は普段服をデザインする中で、平絵という服を平らに置いた状態の設計図のようなものを書いてから型紙へ起こしている。服も様々なパーツを組み合わせ縫い上げることで立体になり、人間が着用できる衣服となる。
建築やインテリアとはまた業界も異なるが、構造的には非常に近い感覚であるなと展示を眺めながら感じた。
第二章に移動すると、フロアや壁紙が黒一色で統一され、一つ一つの家具にスポットライトが当てられており、まるで家具のショールームのようだと感じた。
歩いて進んでいくと、ディスプレイされている作品についての解説が音声で流れて聞こえてくる。耳を澄ましながら隅々まで鑑賞する。

個人的に気になった作品は幾つかあるが、画像中央上の赤のレザーが印象的な壁に取り付けるタイプの椅子は、正面から見ると浮いたように見えるデザイン。
椅子はどこにでも移動できるという概念が私の中にあったが、固定することで建築的要素も垣間見えた。こちらの椅子は実際に暮らしのことを考えると賃貸では利用できない。デザインとして、持ち家で裕福な暮らしをしていることが前提であることが定義できる。そう提案できることもデザイナーとして格好良いと感じた。
第二章をくぐり抜けると、今度はまた明るい部屋へと移り変わる。

こちらのシンプルなデイベッドは、乃木坂にある国立新美術館のフロアにも設置してあるそうだ。
『フリッツ・ハンセン』とブランド名で答えるのではなく、これはポール・ケアホルムがデザインしたのだとさらりと説明できたら箔がつきそう。
さらに奥の部屋「ルオー・ギャラリー」では、実際にケアホルムの椅子に座ることができる。
写真撮影も可能だ。

ラウンジチェアの《PK 4》に座ってみる。ロープでできた座面に座るのは少しばかり緊張感があったが、座り心地は安定しており思ったより体にフィットする。
手前に並ぶ三つのチェアは高さが低く、リラックスチェアのような座り心地。日本での暮らしではなかなか使っている人が少ないイメージだが、サイドテーブルを置いてソファ代わりに利用したい。ゆったり本を読みたい、と想像できた。

汐留美術館へ訪れたのは4度目ほどだが、今回は会場構成がいつもと異なる点があった。それは出口がなく、入口と出口が同じで一つだということ。
実は第二章では、往路ではあまり気づくことのできない仕掛けが施してある。椅子やテーブルが並ぶ展示台の縁周辺にポール・ケアホルムの言葉が添えられている。
もう一度同じ作品をじっくり別角度から堪能できるほか、ケアホルムの考え方を言葉を通じて噛み締めることができる。とても心地の良い展示の締めくくりであった。ポール・ケアホルム展は9月16日まで開催している。会期終盤は特に混雑が予想できるので、ぜひ早めに訪れてみては。