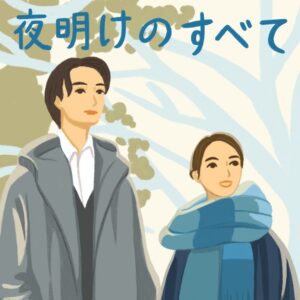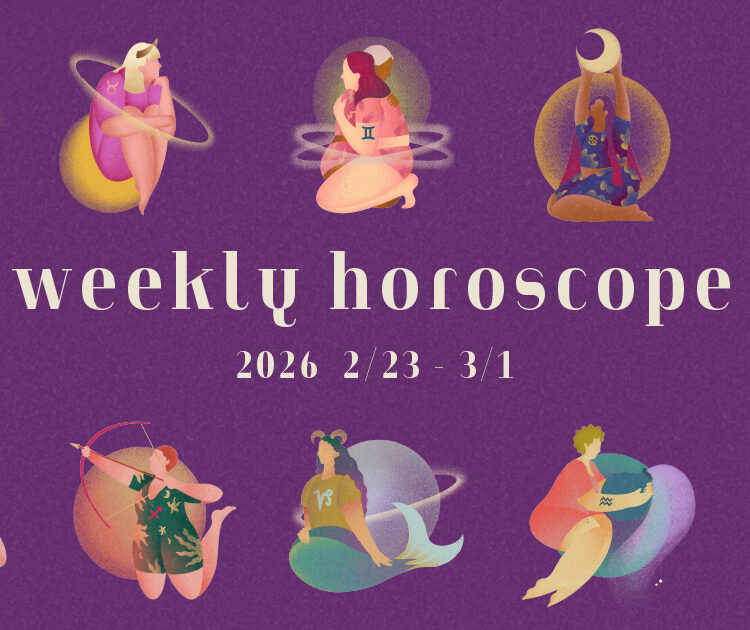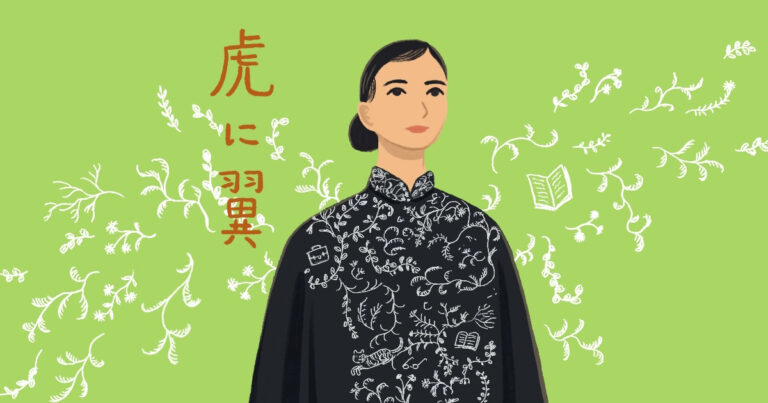
道を切り開く女性だけでなく、その周りの女性を照らすことこそがフェミニズムである。朝ドラ『虎に翼』
配信サービスに地上波……ドラマや映画が見られる環境と作品数は無数に広がり続けているいま。ここでは、今日見るドラマ・映画に迷った人のために作品をガイドしていきます。今回はNHKの朝ドラ『虎に翼』について。
現代において、女性を描く朝ドラにフェミニズムが関わってこないわけがない
日本で初めて法曹界に飛び込んだ女性を描いた朝ドラ『虎に翼』。フェミニズムが随所から感じられるために、それに反論する記事が時折話題になる様子を見て、『アナと雪の女王』(2014年)や『バービー』(2023年)、小説版の『82年生まれ、キム・ジヨン』(2016年)などへの反応を思い出す人も多いだろう。
しかし、日本でフェミニズムをドラマや映画に盛り込んだ作品は、これまでにも少なくなかった。ということは、この『虎に翼』が、これまでよりも話題性があり、フェミニズムがより多くの人に届きやすい形で描かれているということなのだろうか。
『虎に翼』の脚本家の吉田恵里香のこれまでの作品も、『恋せぬふたり』(2022年)では、他者に恋愛感情も性的欲求も抱かない「アロマンティック・アセクシュアル」の男女の物語であるし、『生理のおじさんとその娘』(2023年)では、タイトルの通り生理というものがあまりにも描かれてこなかったことに気付かされる作品であった。その両方に、日常で当たり前のようにされているけれど、実はそこにあった「はて?」という疑問が元になっているように思える。
この「はて?」というのはもちろん『虎に翼』の主人公の猪爪寅子がよく言うセリフである。寅子の「はて?」は、だいたいが「女性とはこうであるべきもの」ということに対しての疑問であり、現代にも「はて?」と思うことがたくさんあるということを思い知らされる。
「こんな朝ドラ見たことがなかった」という評判も多いが、実はこれまでの朝ドラにも、「女性はこうであるべきもの」ということに対しての疑問が描かれるものは多かった。特に『カーネーション』(2011年)は、幼いころから「だんじり」祭りが大好きであったのに、女の子ということで、だんじりに乗る大工方になれない主人公・糸子がミシンという武器を手に入れ、自分の道を進むという物語である。
『虎に翼』の脚本家の吉田も、尊敬する脚本家に『カーネーション』の渡辺あやの名前を挙げており、また『カーネーション』で糸子を演じた尾野真千子が、『虎に翼』でナレーションを担当していることに気付いた時点で、両作品の繋がりを感じた人も多いことだろう。そもそも、現代において、女性を描く朝ドラにフェミニズムが関わってこない方が難しくなりつつあるのではないか。
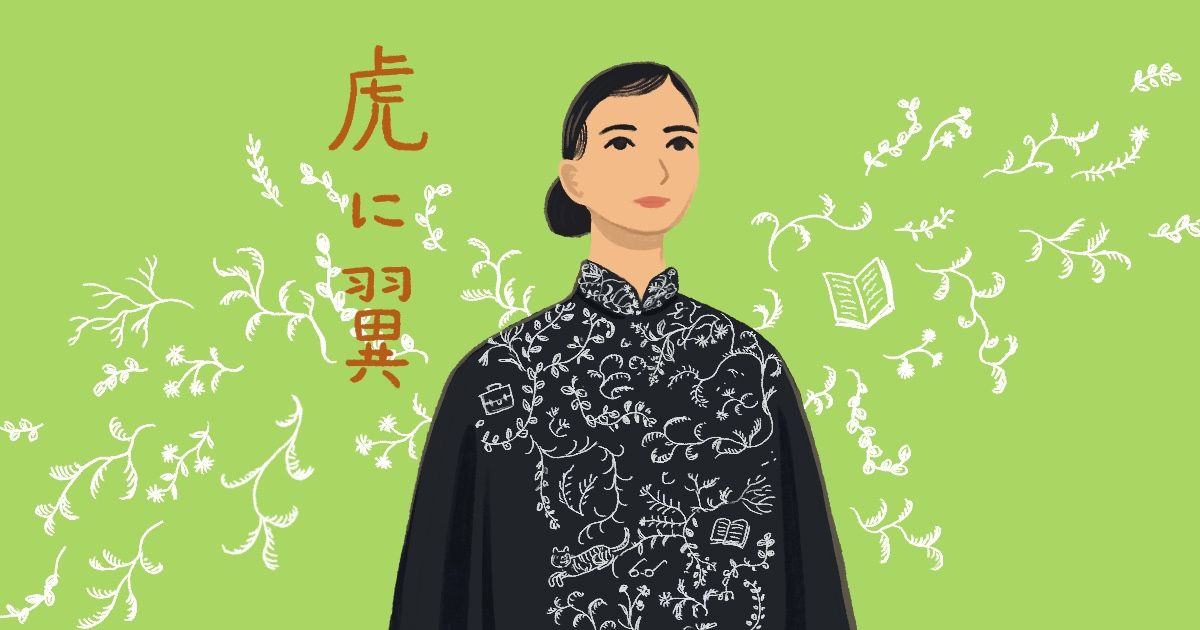
『虎に翼』のフェミニズム描写は、女性が勉学を続けること、弁護士や裁判官になることの困難から始まり、その範囲は多岐に及ぶから、毎週のように書きたいことがあるくらいで、本コラムですべてを書くことは難しいが、なかでも個人的にぐっときたシーンがある。それは、寅子の兄の妻で、寅子の同級生でもある花江(森田望智)とのシーンだ。
寅子や彼女が通う明律大学女子部の面々は、学校で法廷劇を演じるため、その準備のために寅子の家に集まっていた。そのときに顔を合わせた花江を見て、同級生たちは“女中”と勘違い。花江は、これに傷つき、寅子に向かって「いいんです。私なんて女中みたいなもんですから」、「寅ちゃんにお嫁に来た人の気持ちなんて分からないわよ」と言ってしまうのだった。
女性が「私には何もない」と思い込むことも社会的な格差に関係しており、フェミニズムが必要である
『虎に翼』には、寅子のようにストレートに「はて?」と言えない人もたくさん出てくる。寅子の母親のはる(石田ゆり子)は、寅子が婚姻制度に疑問を感じ、結婚がいいものだとは思えないと言ったときに、娘の幸せを考えるからこそ「いき遅れて、嫁の貰い手がなくなって、それがどんなにみじめか想像したことがある?」「頭のいい女が、確実に幸せになるには、頭の悪いふりをするしかないの」と説くが、裁判官の桂場(松山ケンイチ)から、バカにされている寅子を見て「そうやって女の可能性を摘んで来たのは誰?男たちでしょう」と啖呵をきる。矛盾しているようではあるが、はるは「はて?」と思うことを、無理に飲み込んできたが、桂場の言葉によってそれが、噴き出したのだろう。
フェミニズムが、外の世界にどんどん出て、男性とも肩を並べて(という言い方自体に矛盾をはらんでいるが)活躍をしている人だけのものであるとされれば、そこに入れないものたちを置いてけぼりにしてしまう可能性もある。
女性が、「自分には何もない」「人の役に立ったり賞賛されたり、自分を誇れるものがない」と感じ、疎外感を持てば、実は悩みを抱えていても、フェミニズムが助けになると思えず、ますます保守的な考えに固執し、生きづらい方向にいく可能性だってある。『虎に翼』では、こうした寅子の側だけではない女性の気持ちにも寄り添っているところが、個人的には好きな部分である。
実は『光る君へ』でも、「自分には何もない」と考える側に焦点を当てたシーンがある。同ドラマの主人公・まひろは、彼女の父親・為時(岸谷五朗)の妾(しょう)・なつめ(藤倉みのり)の別れた夫の娘であるさわ(野村麻純)と出会い、親友になる。
まひろは裕福ではない家に育ったが、それでも幼い頃から書物に触れ、読み書きができる環境で育った。しかし、さわは父から「おなごは何もするな」と言われ、書物に触れることもなく育ってきた。そのため、まひろに出会って新たな世界を知るも、同時に自分のことを「もの知らずのうつけ」と言うなど、コンプレックスも感じていた。そんな彼女もまた、『虎に翼』の花江のように、「私には才気もなく、殿御をひきつけるほどの魅力もなく、家とて居場所がなく、もう死んでしまいたい」とその気持ちをまひろにぶつけるシーンがある。
ただ普通に懸命に生きている女性たちが、より活躍する女性を見て「私には何もない」と思い込むこともまた、女性が置かれた状況、つまり社会的な格差(ジェンダーにまつわる格差でもある)に関係している。その人たちがいないかのように物語が進むこともあるが、そのような女性たちを描くことも、またフェミニズムであると思う。
奇しくも現在、放送中の朝ドラと大河ドラマに同様のことが描かれていることに驚き、またこれからのフェミニズム表現の可能性を感じた。道を切り開く女性を描くことだけが、フェミニズムではないのである。